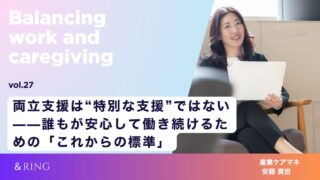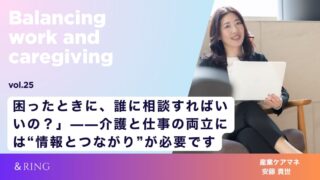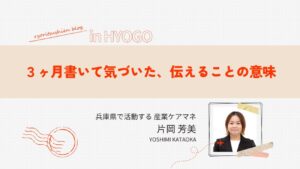#17介護頻度からみた働きながら介護をする者の実態
静岡県で産業ケアマネをしています安藤貴世です🗻
とっても暑い日が続いています。介護をしている方にとっては、お父様お母様の体調が心配される季節です。
特に、エアコンを嫌ったり、温度調節ができない高齢者も多く日々葛藤されているのではないでしょうか。
本日は、久しぶりに「介護頻度」を焦点に働着ながら介護をする皆さんの実態をお話しようと思います。
介護の重さは頻度が関係?
介護」と聞くと、多くの人が「毎日行う重たい負担」を思い浮かべるかもしれません。でも実際には、介護のかたちは人それぞれ。週に数回、買い物や通院の付き添いだけという人もいれば、毎日仕事の後に家に立ち寄って様子を見るという人もいます。
最近の調査では、「働きながら介護している人」の中で、週1回以下の“低頻度介護”をしている人が約4割、週4回以上の“高頻度介護”をしている人が約35%という結果が出ています。(SOMPOインスティチュート・プラス作成、就労構造基本調査(2017)の集計より)
この数字からもわかるように、「介護の重さ」は頻度によって大きく異なります。
今後、75歳以上の高齢者が増加する中では働きながら介護をする人の介護頻度が高い方が増えてくると考えられます。
しかしここで問題なのは、介護は「個別性がある」ということです。
そのため、身体的な介護頻度は高くても会話もでき気持ちは楽に買いをされている方もいれば、軽度な認知症でなんとなく一人での生活はできるが個人の特性から介護をする者の精神的な負担担っていることもあるということもあるのです。
精神的な介護負担は頻度では測れない
週1回の介護であっても、気持ちの上では「常に気にかけている」「いざという時に動けるようにしている」といった“精神的な備え”が続いていることも多いのが実態です。
冒頭での夏のエアコンなどが良い例かもしれません。
つまり、頻度が低くても、常に頭のどこかに介護がある——これが、介護の本質的な負担のひとつです。
職場でも「フルタイムで介護しているわけではないから大丈夫」と思われがちですが、実はその“ちょっとした介護”の積み重ねが、心身の疲労やパフォーマンスの低下に影響しています。
だからこそ、企業や周囲の理解が必要です。
「週に何回介護しているのか」だけではなく、「どんな気持ちで介護に向き合っているのか」「安心して働ける体制があるか」が、これからの両立支援には求められています。
問い合わせ
私、安藤貴世は静岡県にて アンドリング両立支援室 を運営しています。
【業務内容】
・実態調査(アンケートを実施し今後の介護離職の予想などを立てていきます)
・社内研修(ご要望に応じて介護研修を行なっています)
・個別面談(介護に直面している従業員に対してのメンタルヘルスの改善を行なっています)
メール:andring.care@gmail.com
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ1級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護福祉士
介護支援専門員
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 コンサルタント