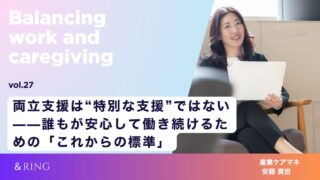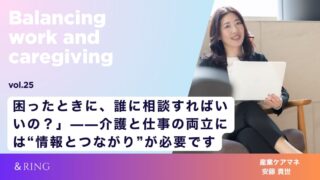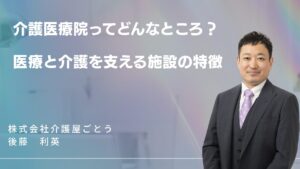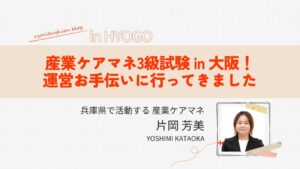#27 両立支援は“特別な支援”ではない——誰もが安心して働き続けるための「これからの標準」
静岡県、山梨県を中心に産業ケアマネをしています安藤貴世です🗻
「介護と仕事の両立支援は、一部の人のための特別対応」——
そんなふうに感じている人が、まだ多いかもしれません。
でも、少し視点を変えてみてください。
今の職場で働く人の中に、すでに親の介護が始まっている人、
これから始まるかもしれない人は、どれくらいいるでしょうか?
実は、ビジネスケアラー(働きながら介護する人)は全国で約364万人。
そして、この数は今後ますます増えると予測されています。
“介護”は誰にでも訪れるライフイベント
介護は、特別な一部の人だけが経験する出来事ではありません。
子育てや病気、家族のサポートと同じように、誰にでも起こりうる日常のひとコマです。
だからこそ、仕事と介護を両立できる環境を整えることは、
「誰かのため」ではなく、「すべての人の未来のため」に必要なのです。
両立支援は“やさしさ”ではなく“経営戦略”
介護離職を防ぎ、経験豊富な人材が職場に残り続けることは、企業にとっても大きなメリットです。
- 生産性の維持
- 離職による人材ロスの防止
- 経験やノウハウの継承
- 従業員満足度・定着率の向上
これらはすべて、組織の安定性と競争力に直結する要素です。
両立支援は「人にやさしい制度」であると同時に、「企業を強くする制度」でもあるのです。
“標準”としての支援を、どうつくるか?
両立支援を当たり前の仕組みにしていくためには、以下のような実践が効果的です:
- フレックス・テレワークなど柔軟な働き方の導入
- 介護休暇や時短勤務制度の整備と“使いやすさ”の工夫
- 社内相談窓口の設置・介護に関する情報提供
- 産業ケアマネなど専門職の活用
- 上司や同僚への理解促進・研修の実施
これらを“誰にでも起こり得ること”として社内文化に組み込むことが、真の意味での「両立支援の標準化」です。
一人の問題ではなく、組織の未来の話
両立支援は「やさしい会社」になるための取り組みではなく、
「安心して働き続けられる職場」を実現するための土台です。
特別ではない、当然の支援として、
“仕事と生活を両立できる”ことが「企業の魅力」となる時代が、もう来ています。
両立支援は、未来の“標準装備”。
あなたの職場も、その準備を始めませんか?
お問い合せ
私、安藤貴世は静岡県にて アンドリング両立支援室 を運営しています。
【業務内容】
・実態調査(アンケートを実施し今後の介護離職の予想などを立てていきます)
・社内研修(ご要望に応じて介護研修を行なっています)
・個別面談(介護に直面している従業員に対してのメンタルヘルスの改善を行なっています)
メール:andring.care@gmail.com
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ1級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護福祉士
介護支援専門員
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 コンサルタント