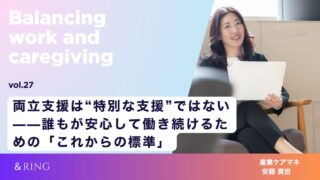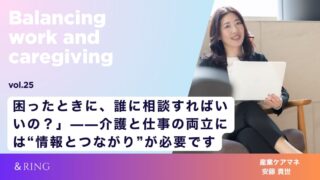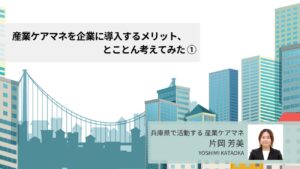#8 80.2%と1.4%
静岡県で産業ケアマネをしています 安藤貴世です🍊
亡き祖母がみかん🍊畑をしており、最近は夏みかんの収穫が楽しみです。
ところで、「80.2%と1.4%」という数字を聞いて、ピン💡と来る方はいらしゃいますか?
実はこれ、育児休業取得率と介護休業取得率を表しています。
80.2%は女性の育児休業取得率(2022年 厚生労働省「雇用均等基本調査」)、1.4%は男女の介護休業の取得率(2022年 総務省「就業構造基本調査」)です。
介護休業の取得率 めちゃくちゃ低いですね😭
制度は整っているのに取得率が低い理由
育児・介護休業法という法律では、介護と仕事の両立を図ることを目的として、介護休業や介護休暇、勤務時間外(残業)の免除、短時間勤務等の両立制度の措置といった様々な制度の導入を会社に義務付けています。2025年の法改正で義務化となりましたが、それ以前から多くの企業では制度導入自体は整っていました。
でも、なぜ制度の利用につながらないのでしょう?
そこにはいくつか理由があると思っています。
1つめは、個別の事情把握の難しさです。育児休業と異なり、介護は本人の申出が無ければ会社や上司が実情を把握しづらい特徴があります。周囲が気付かないため、本人からも相談ができず、結果的に無理をして(打ち明けることなく)働くか、退職してしまうという現実があります。
2つめは、認知度の低さです。育児についての各種制度は知っていても、介護に関する制度は知らない方も多いのではないでしょうか。私も、ご家族様に社内に制度があるか聞いたところ「そんな制度なんてないよ」「制度はあるけど利用している人なんていない」という感じです。どうやって利用するの?どんな時助けになるの?というのが分かりずらいのが認知度の低さになってのが考えられます。
3つめは、介護に直面する方の属性です。仕事をしながら介護をする方のうち、一番多い年齢層は「50~54歳」という結果が出ています。
会社から高いスキルや役割を求められている方や責任ある立場の方も少なくない中で、両立させながら働くことの難しさがあると考えられます。また、この年齢の方は「会社に迷惑をかけたくいない」という心理的ハードルがとても高いです。
理由は他にもたくさんあるかと思いますが、上記のような理由で介護休業はなかなか取得しずらいものになっています。
まとめ
介護は、いつ直面するか分かりません。また、育児と比べて長期化することも多い中で「介護をするか、退職か」という0か100かという選択肢ではなく、「どのように両立させるか」を考えることはとても重要だと考えます。
介護を「特別なこと」にしない職場文化の重要性や制度だけでなく、風土と意識改革が必要ではないでしょか。もしもの時に備えて、まずは情報収集と社内制度の確認を行う必要があるのではないでしょうか。
お問い合わせ
私、安藤貴世は静岡県にて アンドリング両立支援室 を運営しています。
【業務内容】
・実態調査(アンケートを実施し今後の介護離職の予想などを立てていきます)
・社内研修(ご要望に応じて介護研修を行なっています)
・個別面談(介護に直面している従業員に対してのメンタルヘルスの改善を行なっています)
メール:andring.care@gmail.com
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ1級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護福祉士
介護支援専門員
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 コンサルタント