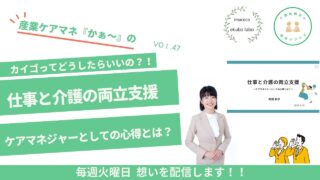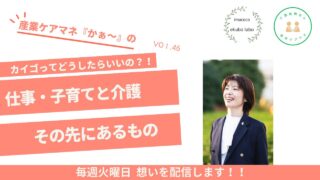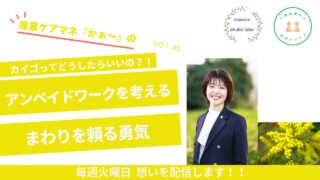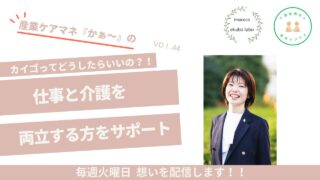頼るということ
仕事と介護の両立の大切さを届けたい
産業ケアマネの
岡田和子です(*^ ^*)

vol.40
今回のテーマは?
頼るということ
みなさん、まわりを頼ることができますか?
上手に頼ることができる人もいれば、なかなかできないことが多いのではないでしょうか?
私は、頼ることが苦手でした。
変な負けず嫌いが働いてしまうところがあり、自分でなんとかしてしまうところがありました。
それが、親の介護が始まった時に、「まわりを頼らなければなんにもできない」と痛感しました。
ましてや、大阪と福岡のように遠く離れていると、頼らないと成り立ちません。
近いと自分がしないといけないの?
子育てをしているときに親が近いと、とても助かりますよね。
例えば、子どもが急に熱を出したときに、仕事中で迎えに行くことができない。
そんなときに、親が迎えに行ってくれると助かります。
しかし、お世話になった親が高齢になり介護が必要になった時、すべてを担わないといけないでしょうか?
人には「思いやり」があります。
お世話になった人に恩返しをしたい。
その思いは大事にしてほしいです。
でも、仕事を辞めて生活のすべてを注ぐことは、これからの介護の方法とは言えません。
仕事と介護の両立
「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」
『仮名論語』 伊與田覺 著
という論語の孔子の言葉があります。
人との和を大切にしながらも自分の信念を持って行動することの重要性を説いています。仕事と介護の両立においても、バランスを保ちながら誠実に取り組むことが求められるでしょう。
君子:道徳的で賢明な人物は、他人と調和を保ちながらも、自分の信念や価値観をしっかり持っている。そのため、他人と同調することなく、独立した考えを持ちながら協力し合う。
小人:道徳的に劣る人物は、他人と同調することを優先し、自分の信念や価値観を持たず、ただ流されるままに行動する。そのため、表面的には協力しているように見えるが、実際には調和が取れていない。
この言葉は、他人と協力しつつも、自分の考えや意志を失わないことの重要性を教えています。仕事や介護においても、自分の価値観を持ちながら柔軟に対応する姿勢が求められますね。
大事にしてほしいこと
確かに、なにかのときに手伝えることは介護する側も喜びとなることもあります。お世話になった親に恩返しができる瞬間でもありますから。
しかし、仕事を辞めて親の介護をするのは、今一度考え直してほしいです。
まずは、自分自身の生活、人生を形成していくことが大切です。
介護が必要になると、登場しないといけないタイミングが出てきます。
それ以外は、介護保険サービスやまわりの方たちを頼っていいんです。
老いていく中で、いろんな場面でリスクが出てきます。予防はできても、おこらないようにすることはできません。そこを、親も子も理解しておくことが大切です。
なぜなら、人はいつまでも、健康で元気に過ごすことはできないからです。
人が終わりを迎えていく過程を知り、どのタイミングでかかわっていくといいのかを知ることが大切です。
まとめ
親が元気なうちに、「仕事を続けながら、できることは手伝うからね」と話をしておいてほしいです。
そのように伝えると、お互いに気が重くならなくていいのではないでしょうか。親も子どもが仕事をつづけることで、社会の役に立っていてほしいと願います。そして、親も子も自律の意識が出てきます。
子ども側は、どこで登場したらいいのかを知っておき、上手に仕事を調整していけば、仕事を辞めずに両立をしていくことができます。
働くことは、本人にとって、企業にとって、社会にとって、日本にとってとても大切です。
介護のこれからのあり方を各世代が知っておくことが必要ですね。
産業ケアマネの岡田和子でした(*^^*)
産業ケアマネは企業と連携して
従業員の方が
仕事とカイゴの両立をできるよう支援いたします。
実態把握のアンケート
介護セミナー
個別相談
従業員の抱えるカイゴに関する課題ついて
企業とともに伴走支援いたします。
お気軽にご連絡ください!
ekubolabo@gmail.com エクボラボ相談室
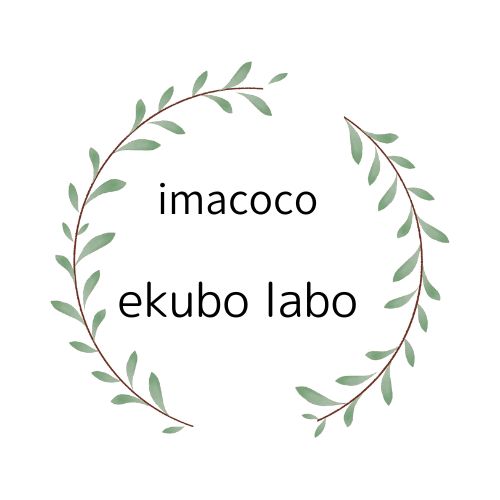
投稿者プロフィール

-
ケアマネジャーを紡ぐ会 大阪支部長
産業ケアマネ2級
主任ケアマネジャー
社会福祉士
メンタルヘルスマネジメント
ヨガセラピスト
THP心理相談員
ホームヘルパー2級 他
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
 コラム2025年3月25日仕事と介護の両立支援~ケアマネジャーとしての心得とは?~
コラム2025年3月25日仕事と介護の両立支援~ケアマネジャーとしての心得とは?~ コラム2025年3月18日仕事・子育てと介護の両立 その先にあるもの
コラム2025年3月18日仕事・子育てと介護の両立 その先にあるもの コラム2025年3月11日アンペイドワーク
コラム2025年3月11日アンペイドワーク コラム2025年3月4日仕事と介護を両立する方をサポート
コラム2025年3月4日仕事と介護を両立する方をサポート