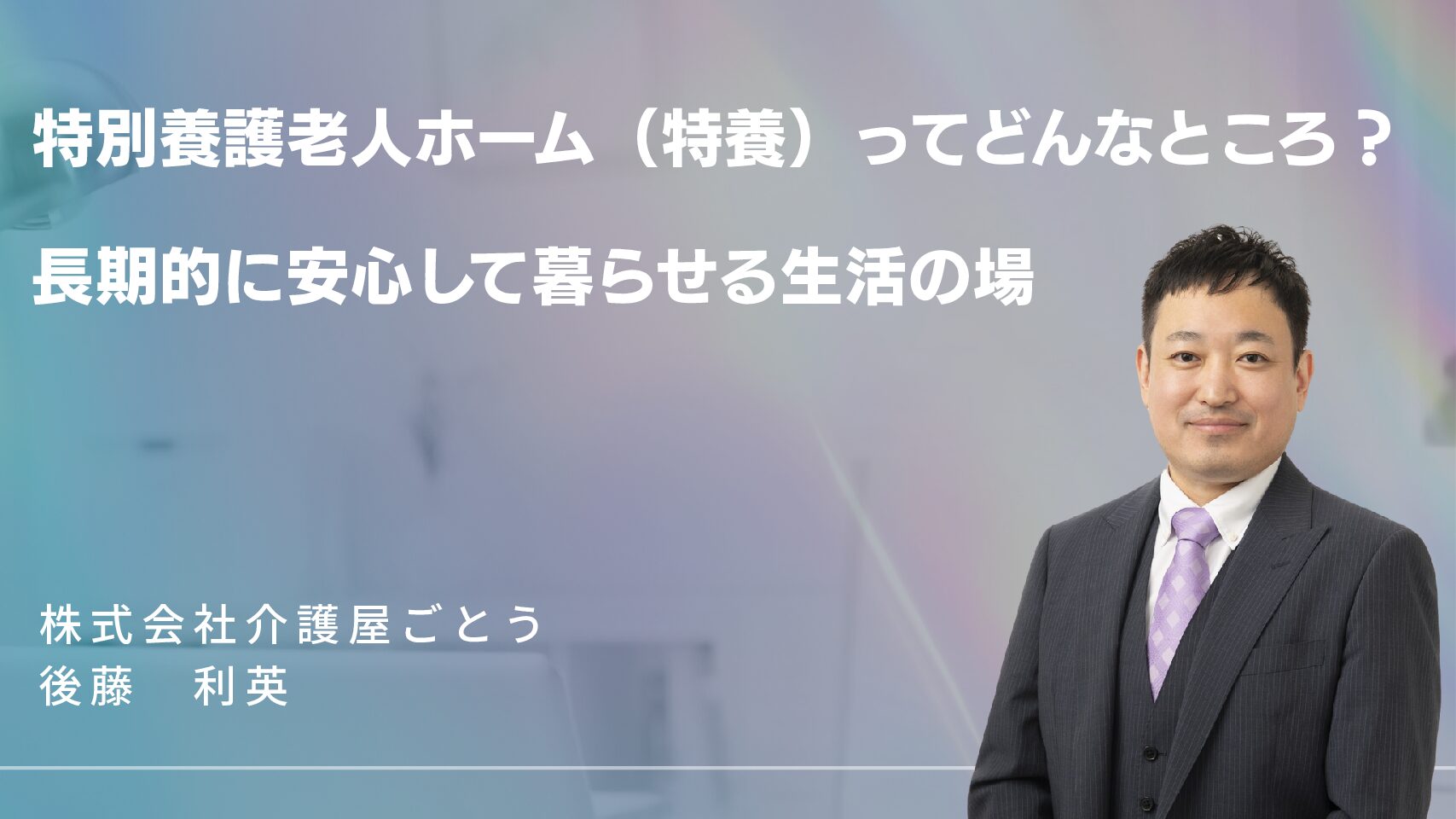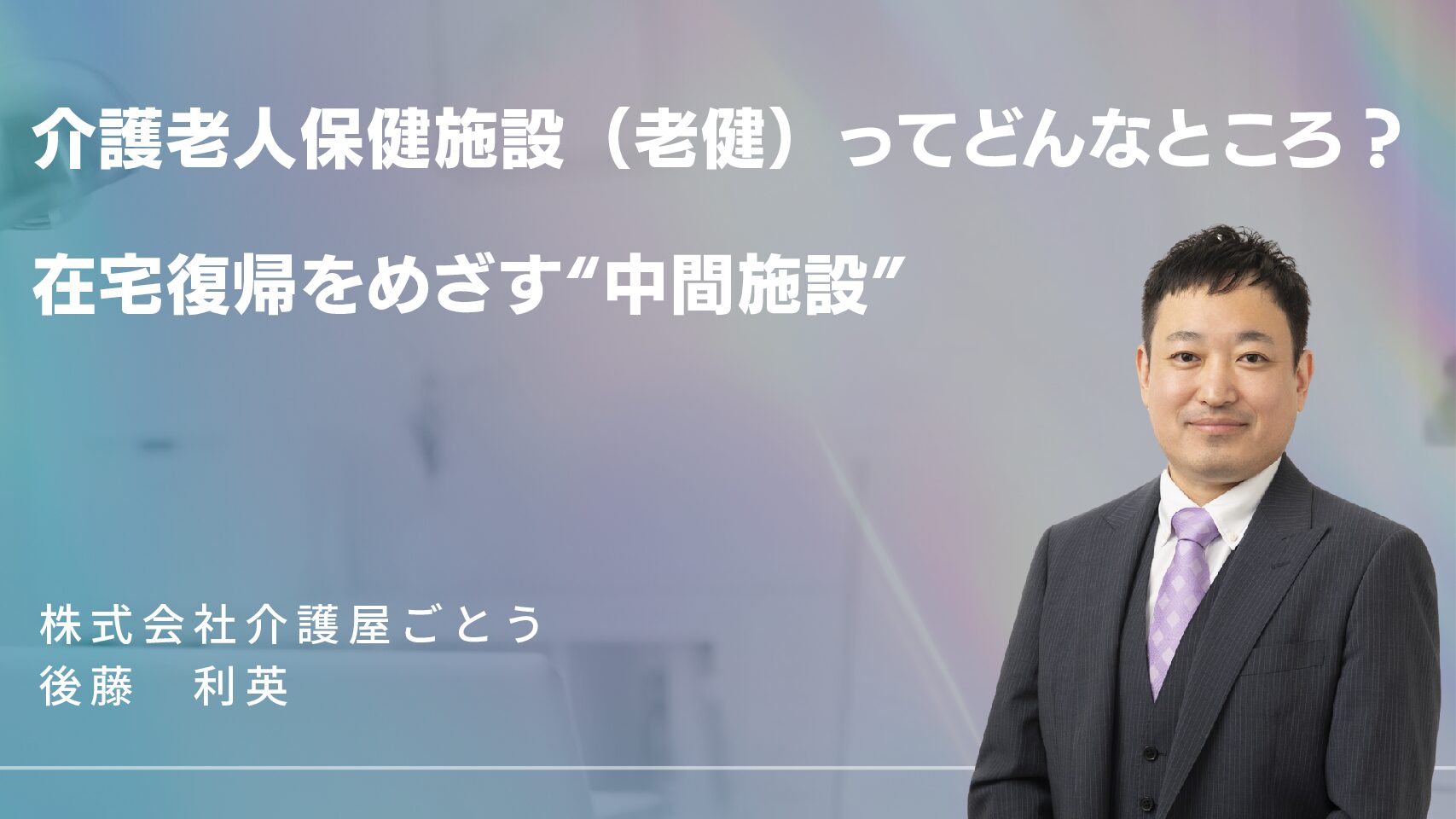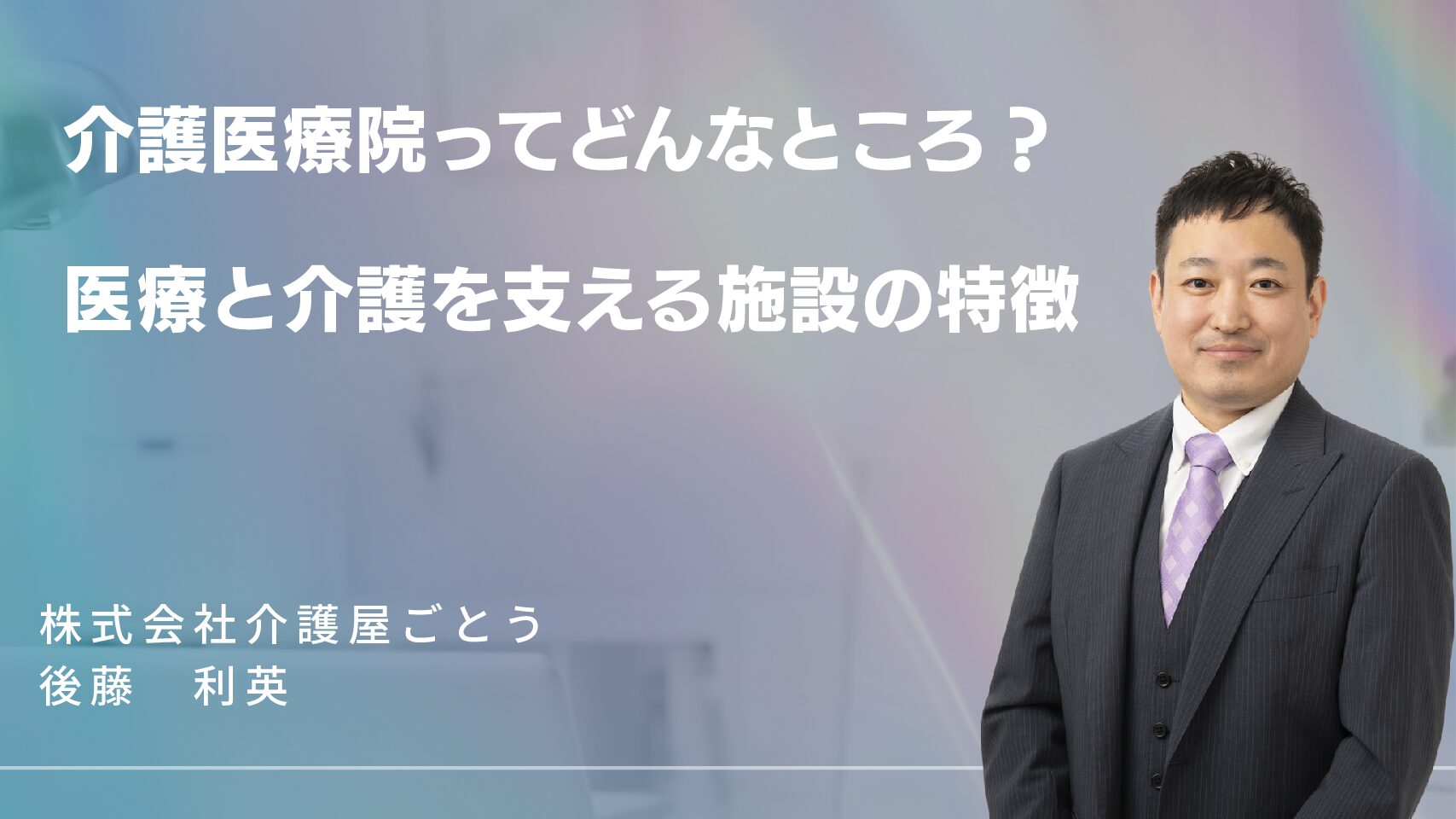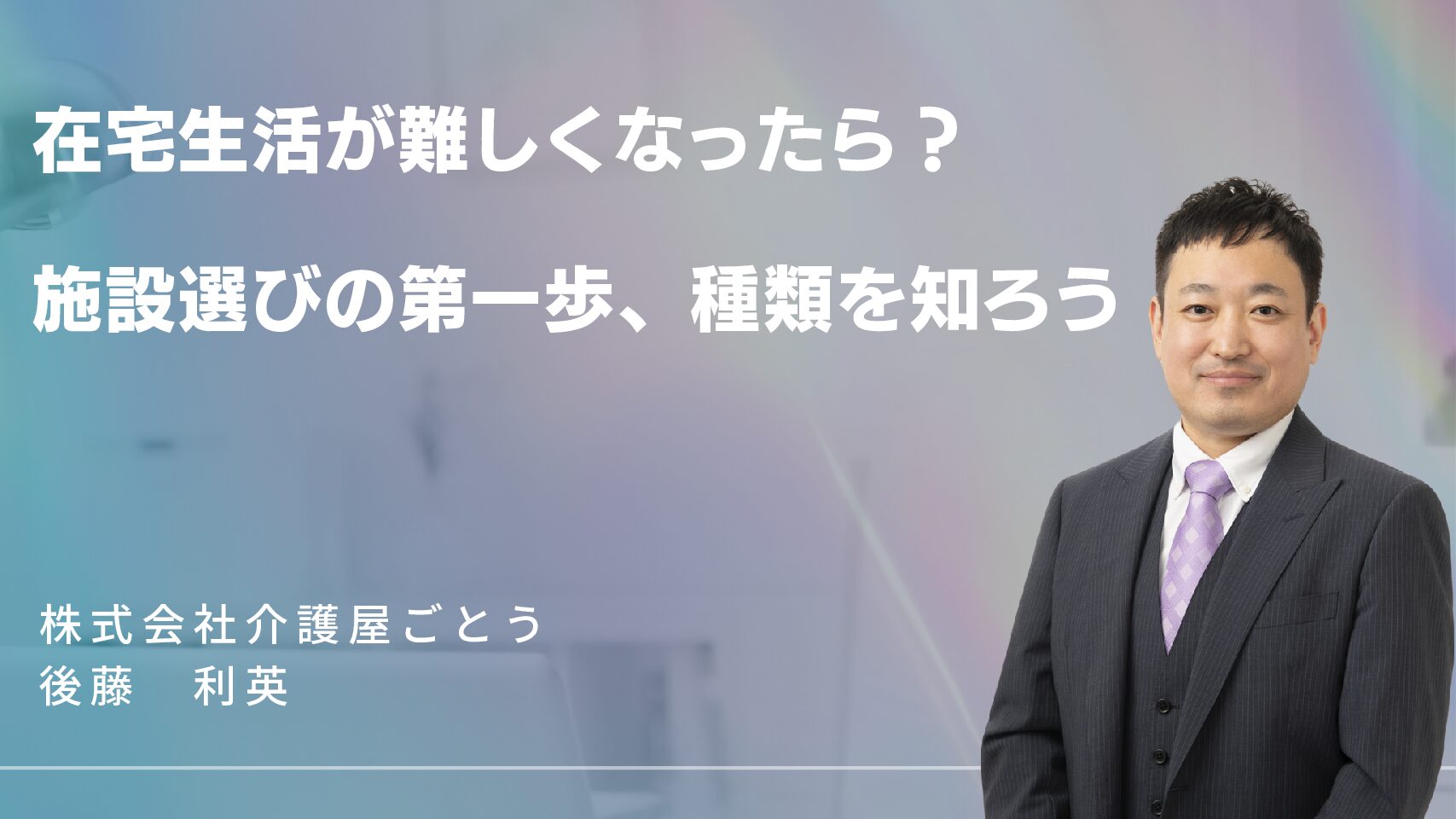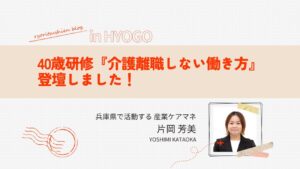在宅か施設か――専門職でも悩み続けるからこそ必要な支え
専門職であっても消えない「悩み」
ある医療従事者の方が、こんな話をしてくださいました。
お母様は認知症を患い、施設に入所されています。調子の良いときにはお子様の名前がわかる程度。食事は経管栄養が中心ですが、時々アイスを食べさせるとむせることが増えてきているそうです。
医療従事者であるため、病状の予後も理解しており、「もう在宅での生活は難しいだろう」と頭では分かっています。それでも、親にとってどこで暮らすのが最善かという問いに、いまだに答えを出せずにいるといいます。
笑わせたい気持ちと現実のはざまで
その方は、週に3回ほど施設への訪問を続けています。行くたびに「必ず1回は笑わせることを目標にしている」と話してくれました。
「医療従事者だから割り切れる」ということはなく、親に少しでも笑顔を届けたいという気持ちと、介護現場の現実の厳しさの間で揺れ動き続けているのです。
これは特別なことではありません。どれほど知識や経験がある人でも、親を前にしたときには「患者や利用者」ではなく「かけがえのない家族」として関わるからです。だからこそ、在宅か施設かという選択に「正解」はなく、誰もが悩み続けるのです。
専門職でも悩むからこそ、相談のつながりを
この話は、介護の専門知識を持たない方にとっても大きなヒントになります。
専門職でさえ悩み続けるのだから、知識のない家族が迷うのは当たり前。一人で答えを出そうとせず、その都度、専門職に相談してよいのです。
ここで役立つのが、医療や介護の現場と職場をつなぐ「産業ケアマネ」の存在です。介護と仕事の両立をどう進めていくか、在宅と施設の選択をどう考えるか、一緒に整理して伴走していきます。
介護の選択は「正解を出す」ことではなく、その時々で納得のいく選択を積み重ねていくことです。産業ケアマネは、そのための支えとなります。
まとめ
介護における「在宅か施設か」の選択に、絶対的な正解はありません。
専門職であっても悩み続けるのですから、一般のご家族が迷うのは当然です。
大切なのは、一人で抱え込まずに、都度相談できるつながりを持つこと。
そして、その伴走者として産業ケアマネが存在しています。
悩みながら選び、支えを得ながら進むことが、仕事と介護を両立していく一番の道なのです。
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう