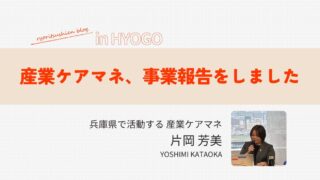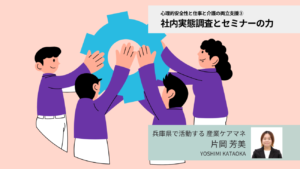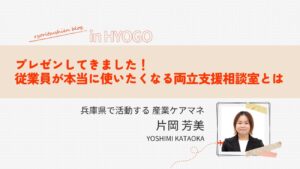心理的安全性と仕事と介護の両立支援④ 心理的安全性が職場全体に広がる効能
兵庫県で活動している 産業ケアマネの 片岡です。
このシリーズでは、介護を抱える社員が声を上げやすくなるための仕組みとして、
- 声を出しにくい理由(第①回)
- 相談窓口と個別面談(第②回)
- アンケートと社内セミナー(第③回)
をご紹介してきました。
今回は、こうした両立支援の取り組みが、介護に限らず職場全体にどのような深い影響を与えるのかを整理してみたいと思います!
介護に限らず多様な場面で心理的安全性を発揮
両立支援によって育まれる心理的安全性は、介護だけにとどまりません。
- 子育て:育児中の社員も、上司や同僚に相談できることで、必要な調整や協力を得やすくなります。
- 病気やケガ:短期・長期の休業や勤務調整もスムーズに行える環境が整います。
- 多様な働き方:在宅勤務や時短勤務など、個々の状況に応じた柔軟な働き方が受け入れられやすくなります。
つまり、社員一人ひとりが「自分の状況を安心して話せる」と感じる環境は、これからの時代、組織のあらゆる場面でプラスに働きます。
信頼関係の深化とチーム力向上
心理的安全性の高い職場では、社員同士の信頼関係が自然に深まります。
- 互いにサポートし合う文化が生まれる
- アイデアや課題を自由に議論できる
- 助け合いの意識が浸透する
結果として、チームは協力的になり、問題解決のスピードも上がります。
さらに、心理的安全性の土台があることで、社員は新しいことに挑戦しやすくなり、イノベーションの創出や業務改善にもつながります。
定着率や組織パフォーマンスへの影響
両立支援は、社員の安心感を生むだけでなく、組織の成果にも直結します。
- 社員が安心して働き続けられることで、離職率が低下する
- チーム内で「誰がどんな工夫をしているか」や「過去の経験から学んだこと」が共有されることで、協力しやすくなり、仕事の効率も上がります。
- 職場の心理的安全性が高まることで、チーム全体のパフォーマンスも底上げされる
つまり、両立支援は単なる福祉制度ではなく、組織開発の重要な一環でもあるということです。
「両立支援=組織開発」の捉え方
重要なのは、両立支援を「介護や子育てに関わる一部の社員向けの制度」と考えないことです。
心理的安全性を育む取り組みとして全社に広げることで、組織全体の文化や信頼関係、働きやすさを高めるツールになります。
言い換えれば、両立支援は個人支援でありながら、組織開発としての側面も持つ――これが現代の職場における大きな価値です。
まとめ
- 両立支援は社員個人の安心感を生むだけでなく、職場全体の心理的安全性を高める
- 心理的安全性の高い職場では、共感・理解・協力が生まれ、チーム力や組織パフォーマンスが向上する
- 「仕事と介護の両立支援」は、組織文化を育て、社員の定着率や創造性にも貢献する重要な取り組み
介護や子育てに関わる社員も、そうでない社員も、誰もが安心して働き続けられる職場――
両立支援は、そのための組織づくりの核となるのです。
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 コラム2026年2月25日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』②まじめな人ほど、仕事と介護の両立が苦しくなる理由
コラム2026年2月25日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』②まじめな人ほど、仕事と介護の両立が苦しくなる理由 産業ケアマネ向け2026年2月21日産業ケアマネ、事業報告をしました
産業ケアマネ向け2026年2月21日産業ケアマネ、事業報告をしました コラム2026年2月18日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』①介護が始まった瞬間、キャリアの分かれ道はもう始まっている
コラム2026年2月18日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』①介護が始まった瞬間、キャリアの分かれ道はもう始まっている 講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像
講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像