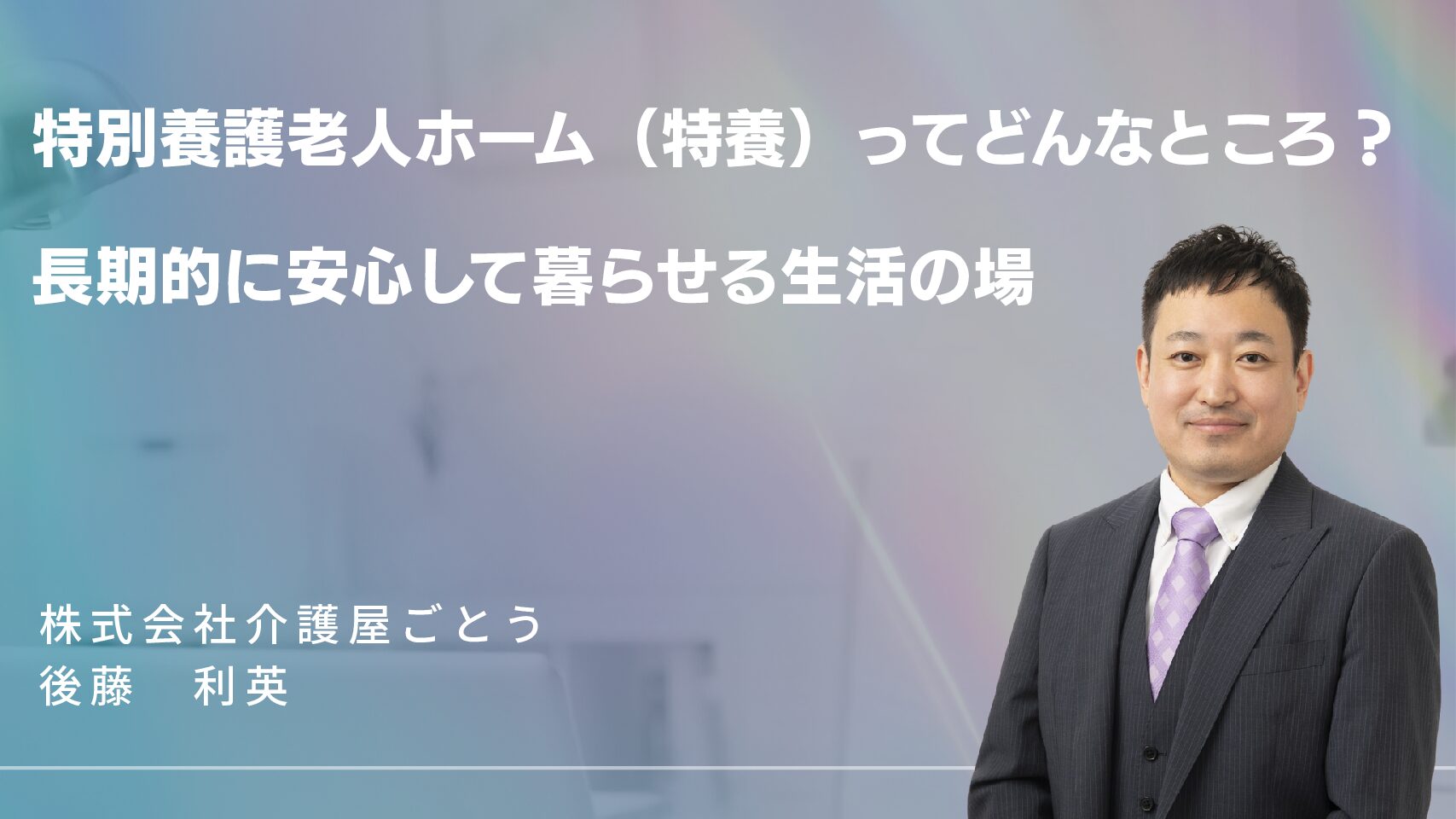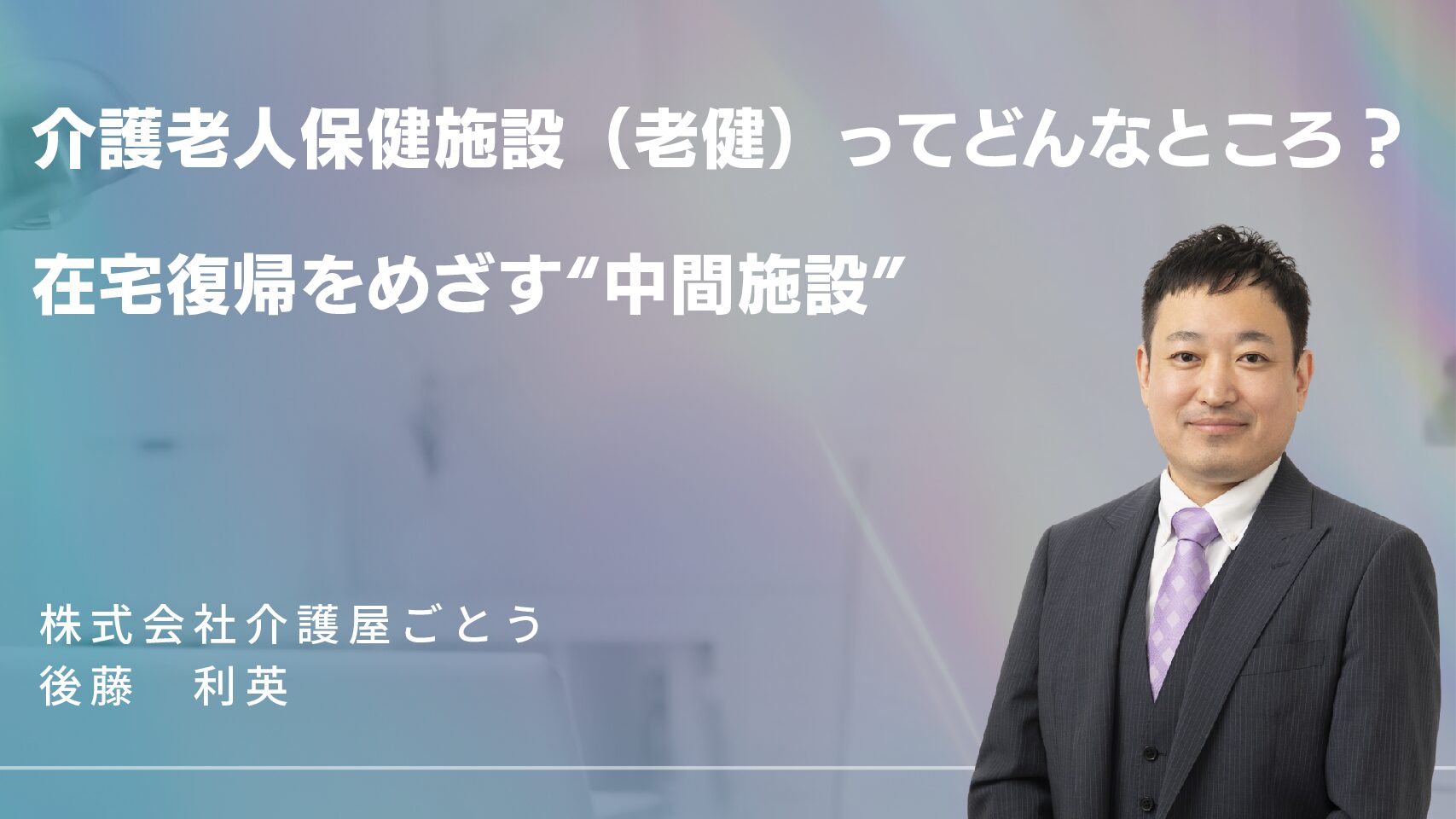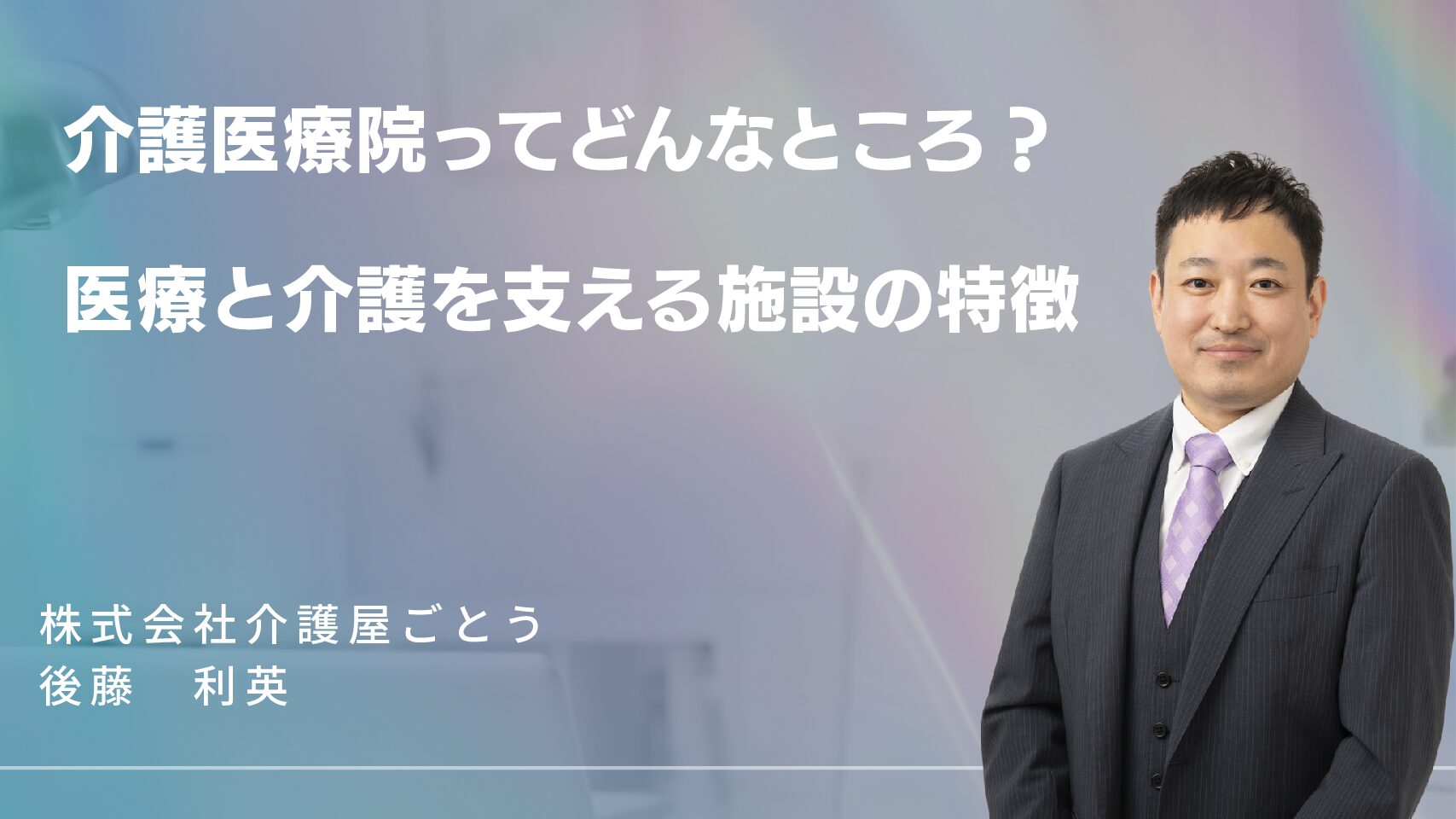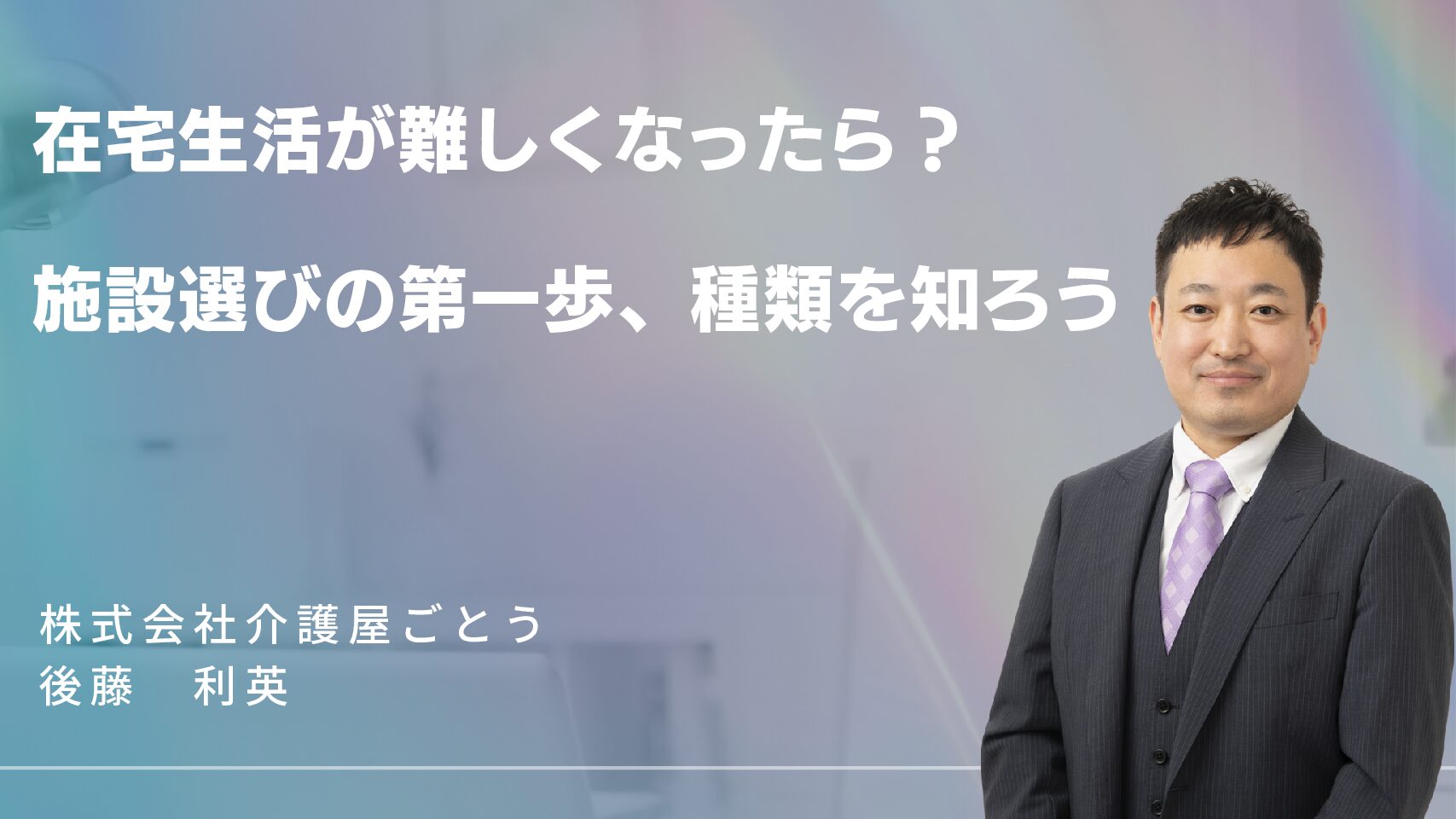親を施設に…それでも踏み切れないあなたへ
― 家族間の“共依存”をほどくために大切なこと ―
「親を施設に入れるのは、申し訳ない」
「最後まで家でみてあげたい」
そんなふうに思うことは、家族として自然な感情です。
けれど、介護には“限界”があります。
仕事をしながら、子育てをしながら、自分の体調とも向き合いながら――
どれだけ頑張っても、心も体もすり減ってしまうことがあるのです。
今回は、私が出会ったあるご家庭をもとに、介護の中で生まれる“共依存”の関係性と、その背景、そしてどう折り合いをつけていくのかを、3つの視点からお話しします。
「もう無理」と思いながらも、決断できない理由
介護を担っているのは長女さんで、お母さまと二人暮らし。
お母さまは認知症が進行し、昼夜逆転、トイレの失敗、夜中の徘徊などもあり、生活はすでに限界を超えている状態です。
「施設に入ってもらった方がいいとは思うんです。でも、やっぱり…」
長女さんはそう言って、なかなか決断に踏み切れません。
周囲も「頑張っていて偉い」と声をかけるだけで、問題の本質に踏み込めずにいます。
本人も苦しく、でも「親を手放すこと」に罪悪感を抱え、
お母さまも「この子がいないと生きていけない」と依存しきっている。
それはもう、「介護」ではなく、“共依存”の関係になってしまっているのです。
周囲は気づいている「限界」。でも本人には言いづらい空気
同居していない家族やケアマネージャー、介護サービス事業所の職員も、
「もう家でみるのは難しいのでは」と感じていることがあります。
実際、長女さん自身も「体力がもたない」「夜が怖い」とこぼしています。
それでも、「お母さんがかわいそう」「自分しかいない」という思いが、決断を遠ざけてしまう。
この状態が長く続くと、
・介護者のうつ症状
・慢性疲労や睡眠障害
・家族関係の悪化や孤立
といった2次的な問題が出てくることもあります。
まわりの人たちも「本人が決めることだから」と遠慮してしまい、“誰も本音を言わない”状況が続いてしまうのです。
「介護から距離を取ること」は、冷たいことじゃない
施設への入居は、「親を見捨てること」ではありません。
自宅では難しい医療管理や24時間体制の見守りを、専門職にバトンタッチするという選択です。
介護を担う側が限界になる前に、環境を変えること。
自分の生活・仕事・家庭を守りながら、「家族としての関係性」を保ち続けること。
それが、本当の“やさしさ”ではないでしょうか。
そして、家から離れたあとも、手紙を書いたり、顔を見に行ったり、施設職員と連携をとったり、できる関わり方はたくさんあります。
距離を取ることは、関係を断つことではありません。
むしろ、新しい形で「関わり続ける」ための、大切な一歩なのです。
【まとめ】
介護は、家族の愛情があってこそ続けられる営みです。
でも、その愛情が“重荷”や“罪悪感”になってしまったとき、
一度立ち止まって「私の人生」「家族全体のバランス」を見つめ直すことが大切です。
介護に正解はありません。
でも、「自分と家族の生活を犠牲にしすぎない」という視点を持つことで、
これからの介護が、もっと続けやすく、支えあえるものになると私は信じています。
あなたのその悩み、どうか一人で抱え込まないでください。
産業ケアマネとして、私たちはいつでも寄り添っています。
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう