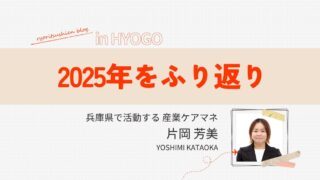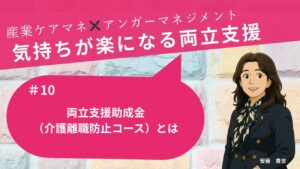仕事×介護 両立の壁 ② 〜情報不足の壁〜
兵庫県で活動している 産業ケアマネ 片岡です。
介護って、「突然始まる」ものばかりではありません。
じわじわ始まっていたのに、気づいたときには家族が限界を迎えていた——
そんなケースも少なくありません。
今回は、情報がないことによって介護サービスの利用が遅れ、長い期間、家族だけで頑張りすぎてしまったケースをご紹介します。
(年齢や家族構成など一部変更しています)
ケース①:介護が必要になったのに、相談先がわからなかったCさん
企業に勤める50代の男性社員。
「母が骨折して入院した。退院後は介護が必要になるらしい」と、慌てて相談に来られました。
退院日も近づいており、仕事との両立ができるかとても不安そうでした。
聞いてみると、介護保険のことはほとんど知らず、要介護認定すらまだ受けていない状態。
「骨折で介護が必要になるなんて思ってもみなかった。もっと早く知っていれば退院後すぐに介護サービスを使えたのに…」と後悔されていました。
ケース②:じわじわ進む認知症と、申請を拒む本人に悩んだDさん
企業で働く50代女性。
「最近、母の物忘れがひどくて…」と、気になりつつも数年間、様子見のまま。
買い物トラブルや金銭管理が怪しくなっても、本人が「元気だから!」と介護保険の申請を頑なに拒否していたため、何も動けず。
次第に家の中での事故や行方不明が増え、Dさんは仕事中も携帯が手放せない状態に。
休みの日には実家通いでヘトヘト、気づけば「退職しようかと思ってる」とまで口にするようになっていました。
早く知っていれば、防げた“しんどさ”がある
これらのケースに共通するのは、「情報さえ知っていれば、もっと早く介護サービスにつながれた」という点です。
✔ 要介護認定の申請は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すれば代行してもらえる
✔ 本人が申請を拒否している場合でも、家族から相談して動き出すことは可能
介護の知識や情報がないことで、必要な支援が遅れてしまい、仕事への影響や家族の負担がどんどん大きくなってしまう…。
だからこそ、「知っているかどうか」が両立の大きな分かれ道になるのです。
情報不足で苦しまないために
介護が始まると、とにかく仕事への影響が出やすくなります。
ただでさえ心身の負担が大きい中、情報不足の状態で仕事と介護の両立を続けるのは、正直かなりハードです。
そんな時、もし職場に「介護」の看板を掲げた両立相談室があったら――
早い段階で「ちょっと相談してみようかな」と思える人が、確実に増えます。
今回ご紹介したような事例からも、知っていれば「もっと早く楽になっていた」「仕事も辞めずにすんだ」人がいることが伝わるのではないでしょうか。
そして、両立支援に必要なのは、国が整備している両立支援制度の説明だけではありません!
介護保険やサービスの活用法、家族としての関わり方まで。
そうした“介護の視点”から働く介護者をサポートすることこそが、実際の両立支援には不可欠なのです。
産業ケアマネがいれば、従業員が抱える介護の不安を早期にキャッチし、必要な支援へつなげることができます。
親の介護を早く“なんとかする”ことが、結果として“いつも通り働ける”道筋になる。
そんな支援を、企業の中でできる存在なんです。
産業ケアマネの導入は、企業にとっても従業員にとっても、きっとハッピーになる社内戦略のひとつ。
これからますます進む高齢社会では、「介護をしながら働く」が当たり前の風景になっていきます。
だからこそ、早めの対策がカギ!
“いざ”が来る前に、備えておきませんか?
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは
講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは コラム2025年12月30日2025年をふり返り
コラム2025年12月30日2025年をふり返り コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン
コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン コラム2025年12月24日2026年の両立計画②年末年始で乱れがちな“心と生活リズム”を整えるセルフマネジメント
コラム2025年12月24日2026年の両立計画②年末年始で乱れがちな“心と生活リズム”を整えるセルフマネジメント