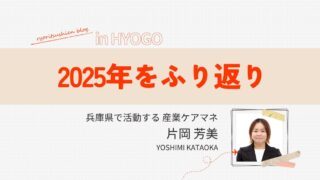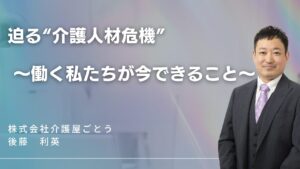「親の介護は子どもがすべき!」と言われた——でもその”こころ”は?
兵庫県で活動している 産業ケアマネ 片岡です。
先日、とある場面でふと投げかけられたひと言。
「親の介護は子どもがすべきよ。」
一瞬、何も言えずにその言葉を飲み込んでしまいました(不覚にも軽くショックを受けてしまったワタシ)。
そうか、やっぱりそう考えている人、今でも多いんだな…。
でもその後、なんとも言えない違和感がじわじわと広がっていきました。
この「親の介護は子どもがすべき」という発言、私が受け取った意味で合ってたのか?
そもそも、“介護”のどこからどこまでを指す発言だったのか?
今回は「親の介護は子どもがすべき」その意味を考えてみたいと思います。
介護って、いったい何をさすの?
介護に携わる専門職であれば皆様ご存知のことと思いますが、「介護」という言葉はとても広い意味が含まれていますよね。
たとえば…
- 食事や排泄、入浴などの身体介護
- 掃除や洗濯、買い物といった家事の支援
- 病院への付き添いや送迎
- 定期的な電話やLINEでの安否確認
- 書類やお金の管理サポート …などなど
人によっては「たまに様子を見に行くこと」も介護だし、ある人にとっては「毎日おむつ交換すること」が介護かもしれません。
「親の介護は子どもがすべき」と言ったその人が、どこまでのことを思い描いていたのかは、わからないまま。
それでも、その言葉が放つ“正しさ”に、心がざわついたのです。
「すべき」の奥にある、いろんな“こころ”
この言葉をあらためて考えてみたとき、ふと思いました。
「子どもがすべき」と言うとき、人はどんな気持ちでそう言うのだろう?
- 親に愛情を返してほしいという願い
- 「家族なんだから当たり前でしょ?」という価値観
- 自分はそうしてきたからという過去の経験からくる言葉
- 介護に対する不安の裏返し
「すべき」という言葉の奥には、いろんな背景がある。
だからこそ、その一言をそのまま受け取る必要はないんじゃないかと思ったのです。
「どう関わるか」は、自分で決めていい
”親の介護をする”を考えた時、一般的にはまだまだ「同居すること」や「排泄や入浴の支援をすること」、「そばにずっと一緒にいること」…などを想像するかもしれません。
でも、家族介護には様々なカタチがあります。
仕事で手が離せなかったり遠くに住んでいても、できる範囲で支援を考える。
定期的に電話で話すこと、サポートの手配・調整をすること、月に一度会いに行くこと——
そんな関わりも、充分「子どもとしての介護」です。
「全部やらなきゃ」じゃなくて、「できることを、できる形で」。
そう思えたら、きっと肩の荷が軽くなると思うのです。
言葉の奥にある“気持ち”と向き合いながら
「親の介護は子どもがすべき」
その言葉の心は「自分なりの関わりでの介護をする」ということだったかもしれません。
でもその言葉は、介護者本人を苦しめるかもしれない。
誰かにとってプレッシャーや罪悪感を生むかもしれない。
そうならないために、自分に合った関わり方を選んでいけるようにすること。
その一言の“こころ”をじっくり見つめること。
産業ケアマネとして「すべき」ではなく「どうしたいか」からはじまる介護を、共に描いていきたいと思います。
迷いや戸惑いがあっても大丈夫。産業ケアマネがここにいます!
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは
講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは コラム2025年12月30日2025年をふり返り
コラム2025年12月30日2025年をふり返り コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン
コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン コラム2025年12月24日2026年の両立計画②年末年始で乱れがちな“心と生活リズム”を整えるセルフマネジメント
コラム2025年12月24日2026年の両立計画②年末年始で乱れがちな“心と生活リズム”を整えるセルフマネジメント