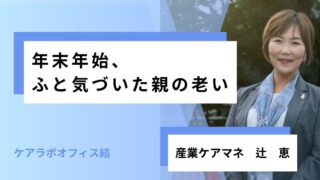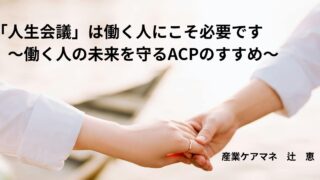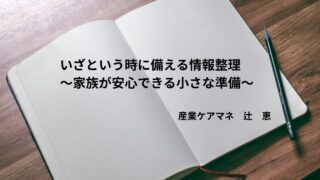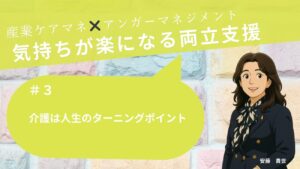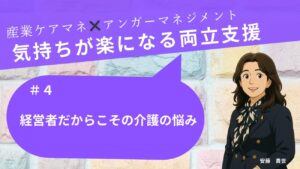男だって介護する時代に
「介護は女性がするもの」――そう思っていませんか?
私も実は昔はそう思っていました。
20年前、夫の両親が相次いで倒れた時、当たり前のように嫁である私が介護することになりました。
そのころは、家庭内での介護は主に妻や娘、嫁が担うというのが一般的だったと思います。
しかし今、その風景は確実に変わってきています。
厚生労働省の統計によると、家族介護者のうち男性の割合は年々増加傾向にあり、現在では全体の3割以上を占めています。特に親の介護を担う中高年の息子たち、いわゆる「男性介護者」が目立つようになってきました。
その背景には、少子化・核家族化・晩婚化といった社会構造の変化があります。
兄弟姉妹が少なく、家族内で介護の担い手が限られる中、「たまたま実家にいる息子」「独身の息子」「定年後に時間ができた夫」などが自然と介護を引き受けるケースが増えているのです。
しかし、「家のことは女性が担うもの」という価値観が根強く残っている中で、男性たちは戸惑いながら介護と向き合っているのが現状です。
仕事と介護の両立に悩む男性たち
特に深刻なのが、仕事と介護の両立に悩む男性介護者の存在です。
介護を担うのは40〜50代の働き盛りが多く、日中は会社で責任ある立場を担い、帰宅後は家族の介護に追われる毎日。
職場に介護の事情を打ち明けにくく、「仕事でも家でも気が抜けない。誰にも弱音を吐けない」と話す男性介護者の声は、決して珍しくありません。
介護のために、早退したり休んだりすることで、同僚や部下に仕事の皺寄せがいき、会社に迷惑をかけるのではないかと心配になります。
介護も仕事も中途半端な状態になるし、そんなことならいっそのこと仕事を辞めてしまおうと、仕事を辞める介護離職する男性が増えているのです。
また、これは私の主観ですが、私がケアマネジャーとして関わってきた男性介護者は「人に頼るのが苦手」「相談するのが恥ずかしい」という方が多いように思います。介護を1人で抱え込んでおられる方も少なくありません。
その結果、介護疲れやうつ状態、場合によっては共倒れのリスクまで高まるのです。
男性介護者が声を上げられる社会へ
そんな中でも、「親の最期を自分の手で見届けたい」「できることはやりたい」と、真摯に介護に向き合っている男性介護者もおられます。
中には、「介護を通して親との距離が縮まり、家族としての関係が深まった」と話す方も。
介護は辛さだけではなく、家族の絆を見直す機会にもなりうるのです。
最近では、「男性介護者の会」や「介護男子ネットワーク」など、男性同士が悩みを共有できるコミュニティも広がっています。
そして、企業でも介護と仕事の両立支援制度を導入する動きが進んでいます。
職場でも、家族の介護について話せる場所が必要です。
家族の介護にきちんと向き合いながらも、仕事のパフォーマンスを落とさないために
まずは誰かに相談できる場所。
会社の中の「介護の相談窓口」
これこそが、責任感のある男性介護者の駆け込み寺になるかもしれませんよ!
そして、今や女性の社会進出も進み男女関係なく、仕事も介護も役割分担する時代となりました。
介護は“誰かの役割”ではなく、必要な人が支え合っていくもの。
性別に関係なく、誰もが無理なく役割を担える社会をつくっていくことが求められていると思います。
産業ケアマネは、企業内での介護の相談窓口として個別相談に応じます。
詳しいことを知りたい方は下記までお問い合わせくだい。
私は産業ケアマネとして、企業の経営者及び人事担当の方々、そして一般の方を対象に介護セミナーを行っています。
ご興味のある方は、下記までお知らせください!
↓ ↓ ↓ ↓
cm.megumi0925@gmail.com
ポートフォリオとプロフィール
↓ ↓ ↓ ↓
https://note.com/cm_kinako/n/n1809272508c7
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 1期卒業生
ケアマネージャー歴 10年
社会福祉士
介護福祉士
保育士
最新の投稿
 コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い
コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い 産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜
産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜 コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜
コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜 コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜
コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜