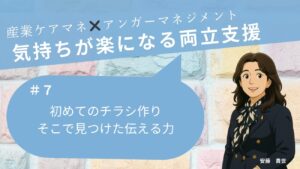364万人が働きながら介護する社会
みなさん、こんにちは。
奈良市を拠点に、ケアマネジャーおよび産業ケアマネとして活動している山﨑です。
日々の支援を通して感じているのは、「働きながら介護を担うご家族」が年々増えているという現実です。
その多くは、家族の中で自然とキーパーソンとなり、介護の中心を担う立場に置かれています。
今回は、そんな現場で見えてきた“いまのリアル”を、私なりの視点で綴ってみたいと思います。

全国で364万人が「働きながら介護」をしているという現実
2025年4月、改正育児・介護休業法が施行されました。
この法改正の背景には、「仕事と介護を両立している人が実に多い」という現実があります。
ケアマネジャーをとして訪問をしても、働きながら介護をしているご家族に当たり前のようにお会いします。
総務省の『令和4年 就業構造基本調査』によると、全国で介護をしている人は約628万人。
そのうち、仕事をしながら介護をしている「有業者」は約364万人にのぼります。
つまり、介護者の約6割が“働きながら介護している”という状態にあるのです。
法改正のポイントー「個別対応の義務化」と「テレワークの努力義務」
今回の法改正では、企業が取るべき対応が明確に定められました。
- 介護に直面した従業員に対して、制度の周知と意向確認の実施(義務)
- 在宅勤務(テレワーク)の導入に関する措置の努力義務化
これは、介護をしながら就業を継続するための具体策として、国が企業に対して“働き方の柔軟性”を求め始めた重要な一歩と言えます。
産業ケアマネは、こうした制度改正の背景を企業に伝え、実際に支援に結びつける役割を担いますが、注意しなければいけないことがあります。
テレワーク介護の落とし穴 〜意外と見落としがちな3つのこと〜
テレワークは便利な一方で、介護と距離が近すぎることで次のような課題が生まれます。
- つい親の世話をしてしまう
仕事中でも親の様子が気になり、声をかけたり介助に手が出てしまう。 - 予定通りに進まない
突発的な介護対応で、会議や作業時間が崩れがち。仕事の集中が保てなくなる。 - 気持ちの切り替えが難しい
通勤がない分、「今は仕事」「今は介護」と頭を切り替えるのが難しく、ストレスが蓄積しやすい。
「家にいる=両立しやすい」とは限らず、意識と仕組みづくりが求められます。
両立を“自然に”するには、環境の工夫と第三者の支援(産業ケアマネなど)も効果的です。
親との向き合い方と介護との向き合い方を分ける
大切なのは、「介護とどう向き合うか」という姿勢です。
介護は、ただの“お世話”ではなく、感情や関係性、時間や体力など、さまざまなものが交差する複雑な営みです。
だからこそ、一人で抱え込みすぎないことが何よりも大事になります。
「親が困っているから」と思う気持ちは尊いものですが、それが続くと心や体に無理が生じ、介護も仕事も辛くなってしまうことがあります。
頼れる制度や人、サービスに手を伸ばすことは、決して弱さではありません。むしろ、それは“続けていくための知恵”であり、“自分自身を大切にする行動”だと思います。
少しでも心に余白を持てると、介護も仕事も、前向きな気持ちで取り組めるようになります。
その余白こそが、両立の鍵であり、私たち一人ひとりに必要な“ゆとり”なのかもしれません。
5月は制度の「説明」から「活用」へ──職場の文化として根づかせるための支援が始まっています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは、
今日も素敵な1日になりますように!
それでは、今日も素敵な1日になりますように!
投稿者プロフィール

-
介護現場18年
株式会社介護屋山﨑 代表取締役
奈良県介護支援専門員法定研修講師
一般社団法人日本単独居宅介護支援事業所協会 ケアマネジャーを紡ぐ会 奈良支部長
詳しいプロフィールはこちら
最新の投稿
 産業ケアマネ向け2025年12月15日産業ケアマネ1級養成講座 2日目
産業ケアマネ向け2025年12月15日産業ケアマネ1級養成講座 2日目 コラム2025年12月1日産業ケアマネ1級養成講座開講!
コラム2025年12月1日産業ケアマネ1級養成講座開講! 産業ケアマネ向け2025年8月20日第4期「仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座」第4日目レポート〜産業ケアマネが企業に届けるアプローチの力〜
産業ケアマネ向け2025年8月20日第4期「仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座」第4日目レポート〜産業ケアマネが企業に届けるアプローチの力〜 産業ケアマネ向け2025年7月15日仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座・3日目
産業ケアマネ向け2025年7月15日仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座・3日目