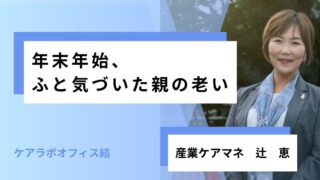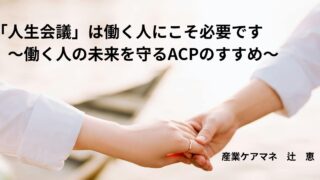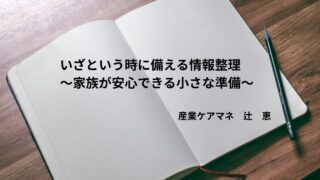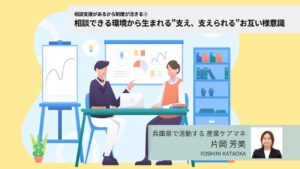親の思いを聴く時間〜ACPをはじめる第一歩〜
こんにちは!
現役ケアマネジャーとして日々ご利用者の支援を行いながら、
「産業ケアマネ」として仕事と介護の両立支援プログラムを実施している辻 恵(つじ めぐみ)です。
社内セミナーで介護に関する基礎知識をお伝えしたり、
社員の方からの「親の介護、そろそろ心配で…」というご相談をお受けしたりしています。
先日のブログ「ACP(人生会議)〜介護が始まる前にできる3つのこと〜」では、
介護が始まる前に話す・備える・つながるの3つを意識しておくことの大切さについてお伝えしました。
今回はその中でも、最も大切でありながら後回しにされがちな「親の思いを聴く時間」について、少し深掘りしてお話しします。
親の「思い」を聴くということ
介護の仕事をしていると、「もっと早く親の気持ちを聴いておけばよかった」とおっしゃるご家族に出会うことがあります。
元気なうちは、まだ先の話と思いがちですが、いざという時は突然やってきます。
だからこそ元気な今が話せるチャンスなんです。
「親の思いを聴く」というと少し構えてしまうかもしれませんが、
難しく考える必要はありません。
たとえば、「これからどんなふうに暮らしたい?」「介護が必要になったら、どんな形がいい?」
そんな問いかけからでも十分です。
大切なのは、親の価値観を知ること。
その思いを知っているだけで、将来の選択に迷ったとき、家族の判断がぐっと楽になります。
ケアマネとして感じた「聴く力」の大切さ
以前、担当していた80代の女性のケースでのことです。
その方は、元気なうちから娘さんとよく話をされていました。
「できるだけ自分の家で暮らしたい」「でも娘には迷惑をかけたくない」と。
介護が必要になった時、娘さんはその言葉を胸に、在宅とデイサービスを上手に組み合わせて支援を続けておられました。
ある日、娘さんが私にこう話してくれました。
「母の気持ちを聴いていたから、迷わず選択できたんです。あの会話がなかったら、きっともっと悩んでいました。」
この言葉を聞いたとき、ACP(人生会議)は準備というよりも、親子の信頼を育む時間なのだと改めて感じました。
聴く時間をつくるコツ
とはいえ、いきなり「将来の話をしよう」と切り出すのは難しいですよね。
そんなときは、日常の会話の中でさりげなく始めてみましょう。
たとえば、
テレビで介護の話題が出たときに「お母さんならどうしたい?」と聞いてみる。
あるいは、昔の話を聞く中で「お父さんはどんな生き方が理想?」と尋ねてみる。
家族だからこそ、改めて言葉にしないと思いがすれ違うこともあります。
会話の中で出てきた親の言葉は、メモに残しておくと良いですよ。
きっとそれが、将来家族みんなの支えになるはずです。
おわりに
「親の思いを聴く時間」は、介護の準備ではなく、心の準備です。
それは、親の人生を尊重し、家族の絆を確かめる優しい時間。
そして仕事と介護を両立するためにも、早めに話しておくことで、
家族の選択が前向きで納得のいくものになります。
次回は、「ACP今からできる3つのこと」シリーズの第3回として、
「いざという時に備える情報整理」についてお話しします。
📘 私は産業ケアマネとして、職場で「仕事と介護の両立支援プログラム」を実施しています。
https://docs.google.com/document/d/1Ha9sTImbPJNpwPNtqBuiks2QInl34J9E_hequjrbZg8/edit?tab
また、社内外で介護やACP(人生会議)をテーマにしたセミナーや講演活動も行っています。
“介護をきっかけに、家族や自分の生き方を見つめ直す時間”を届けたいと思っています。
💌 介護に関するご相談やセミナーのご依頼などがありましたら、
https://forms.gle/S4SKvoPkYq2n9Z
こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 1期卒業生
ケアマネージャー歴 10年
社会福祉士
介護福祉士
保育士
最新の投稿
 コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い
コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い 産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜
産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜 コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜
コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜 コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜
コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜