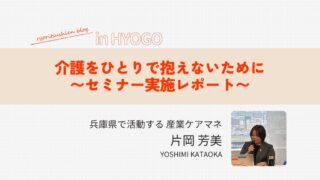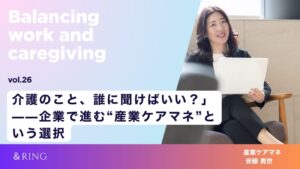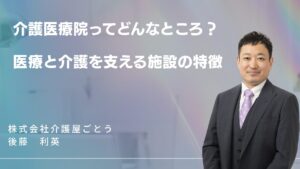心理的安全性と仕事と介護の両立支援① なぜ「両立支援」が心理的安全性につながるのか
兵庫県で活動している 産業ケアマネの 片岡です。
「心理的安全性」という言葉を耳にされたことがあるでしょうか。
これは、「自分の意見や考えを安心して話せる状態」を指します。
心理的安全性が高い職場では
・失敗を恐れずに挑戦できる
・意見の違いを建設的に議論できる
・互いにサポートし合える
これらの行動が自然と生まれ、社員一人ひとりの声が活かされ、チーム全体の力が高まります。
そして実は、仕事と介護の両立支援を考えるうえで、この心理的安全性がとても重要です。
なぜなら、介護を抱える社員は「声を出すこと」自体に大きなハードルを感じているからです。
介護が「言いにくい」3つの理由
①プライベート色が強いから話しづらい
介護は家庭内の出来事であり、本人も「職場に持ち込むべきではない」と思い込みがちです。
「親のことを同僚に話すのは気が引ける」という心理的な壁もあります。
②周囲に迷惑をかける不安
「介護を理由に休めば同僚に負担がかかるのでは…」という不安。
その思いから、ギリギリまで誰にも相談せず抱え込んでしまうケースは少なくありません。
③情報不足による孤立
介護保険や社内制度を知らないまま、「自分でなんとかしなければ」と背負い込んでしまう。
情報不足は焦りや孤立感を強め、ますます声を出しにくくします。
声を出せないとどうなるか
「言えないまま時間が過ぎる」と、支援が後手に回ります。
結果として、
・業務のパフォーマンス低下
・突発的な休職
・最悪の場合、離職
これらに繋がりかねません。
本人もチームも疲弊し、職場全体に負の連鎖が広がることもあります。
心理的安全性があれば変わること
一方で、「困ったときは相談できる」という安心感がある職場ではどうでしょうか。
・早い段階で声をあげられる
・上司や同僚が事情を理解し、協力体制を作りやすい
・本人は仕事を辞めずに介護と両立できる
・結果的に会社も損失を最小化できる
このように、良い循環を生み出すことができます。
両立支援で職場の「心理的安全性」を高めよう
介護は誰にでも起こり得るライフイベントです。
社員が声を出しにくい現実を理解し、安心して相談できる職場をつくること。
これが「心理的安全性」と「仕事と介護の両立支援」を結びつける第一歩です。
両立支援を充実させるということは、職場の心理的安全性を高めることにもつながります。
それは介護に直面した時だけでなく、普段の業務にも良い影響を及ぼし、職場のチーム力を底上げする取り組みなのです。
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像
講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像 講座2026年2月4日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る④個人の準備をしておく(情報・家族・お金)
講座2026年2月4日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る④個人の準備をしておく(情報・家族・お金) セミナー2026年1月31日介護をひとりで抱えないために〜セミナー実施レポート〜
セミナー2026年1月31日介護をひとりで抱えないために〜セミナー実施レポート〜 講座2026年1月28日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る③介護者の「仕事を守る」ことが、在宅介護を守る
講座2026年1月28日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る③介護者の「仕事を守る」ことが、在宅介護を守る