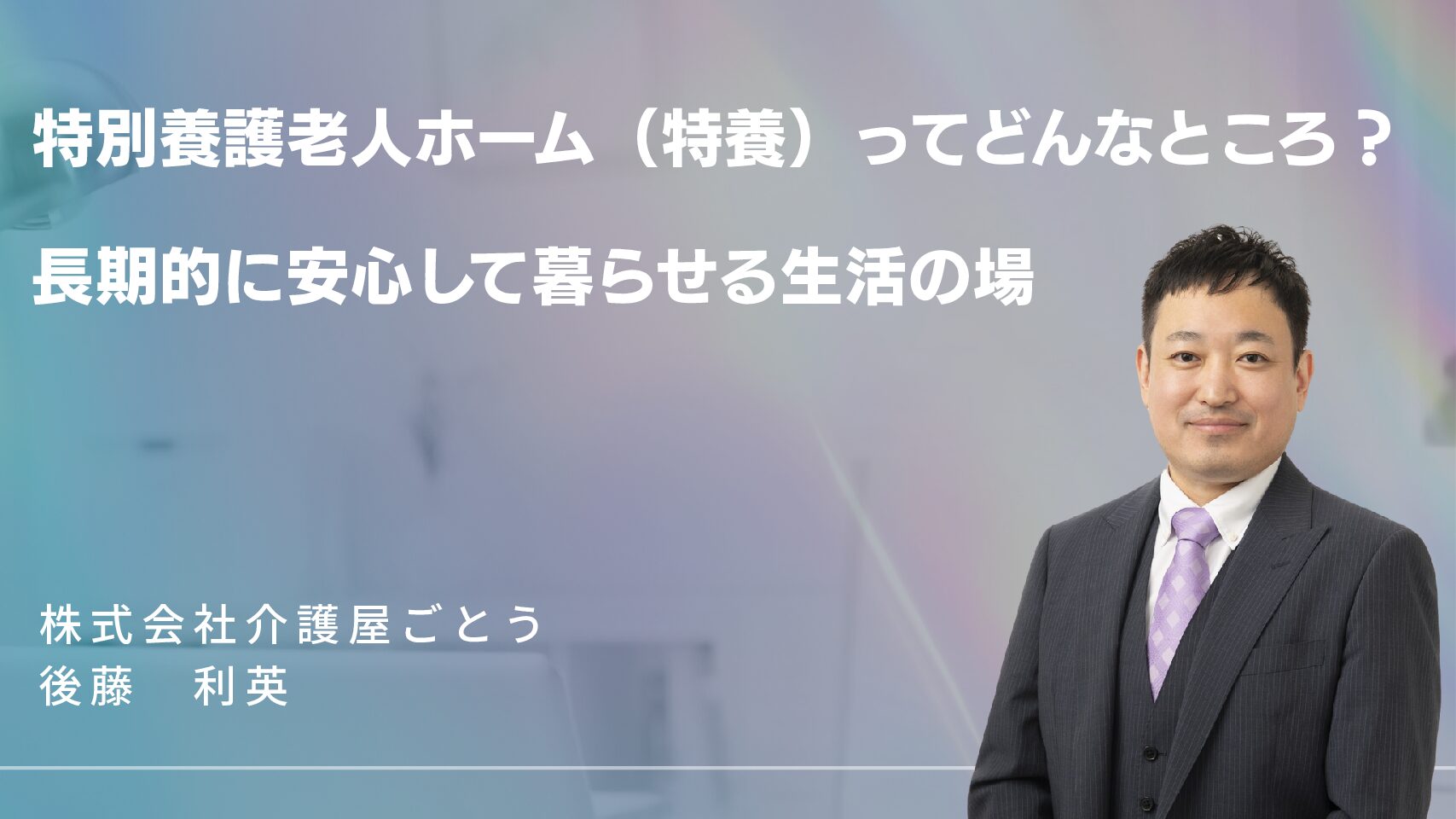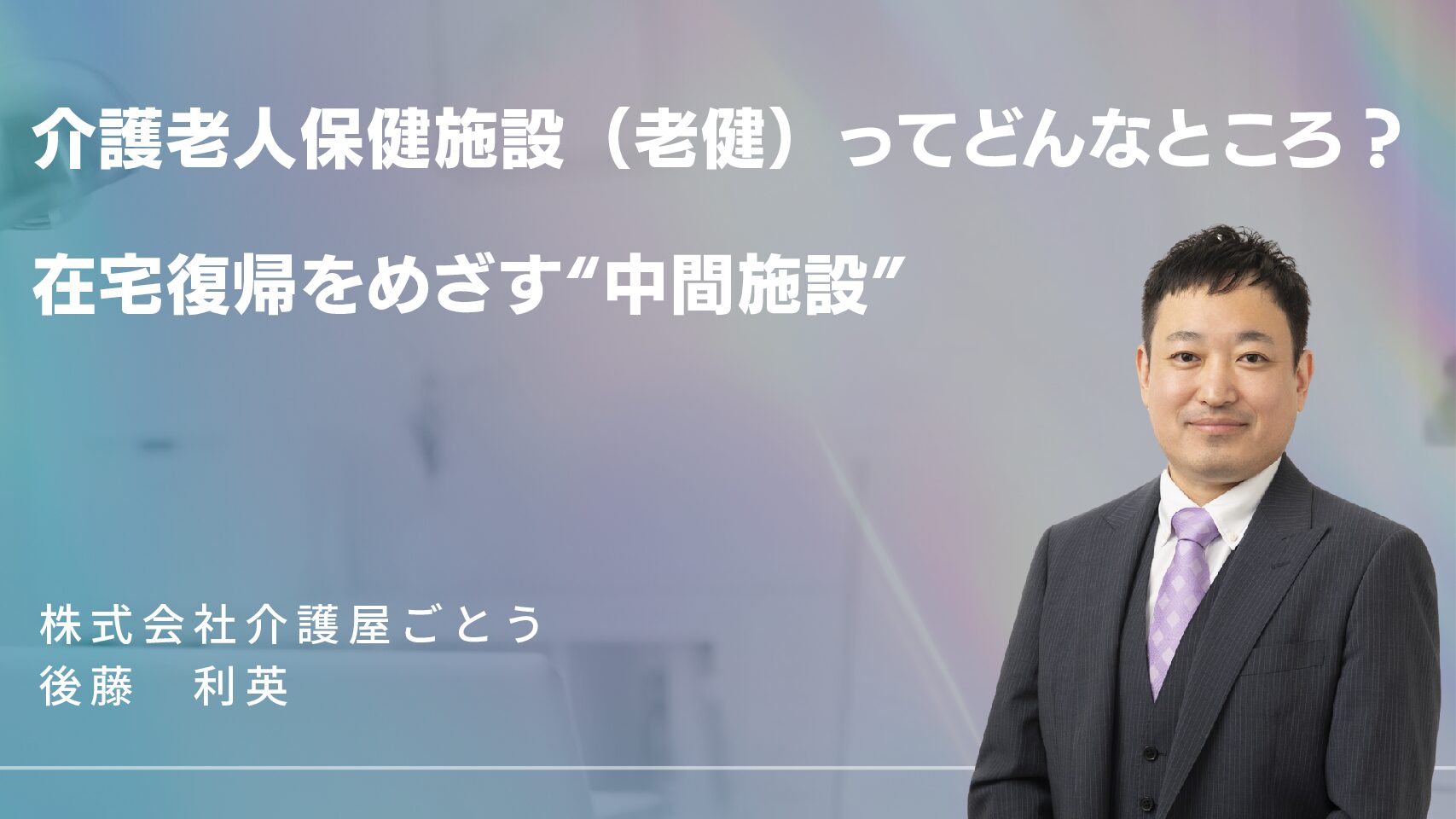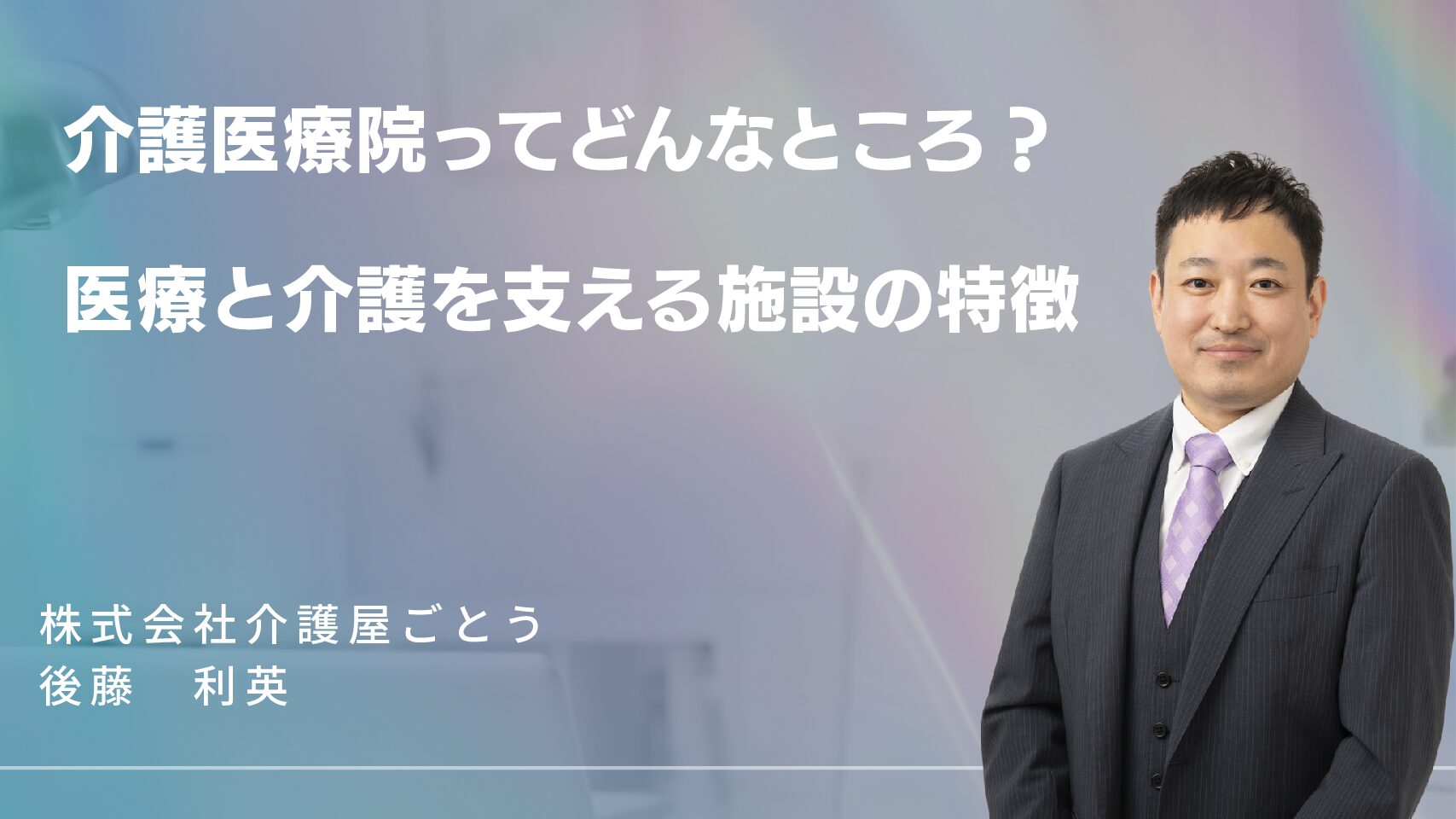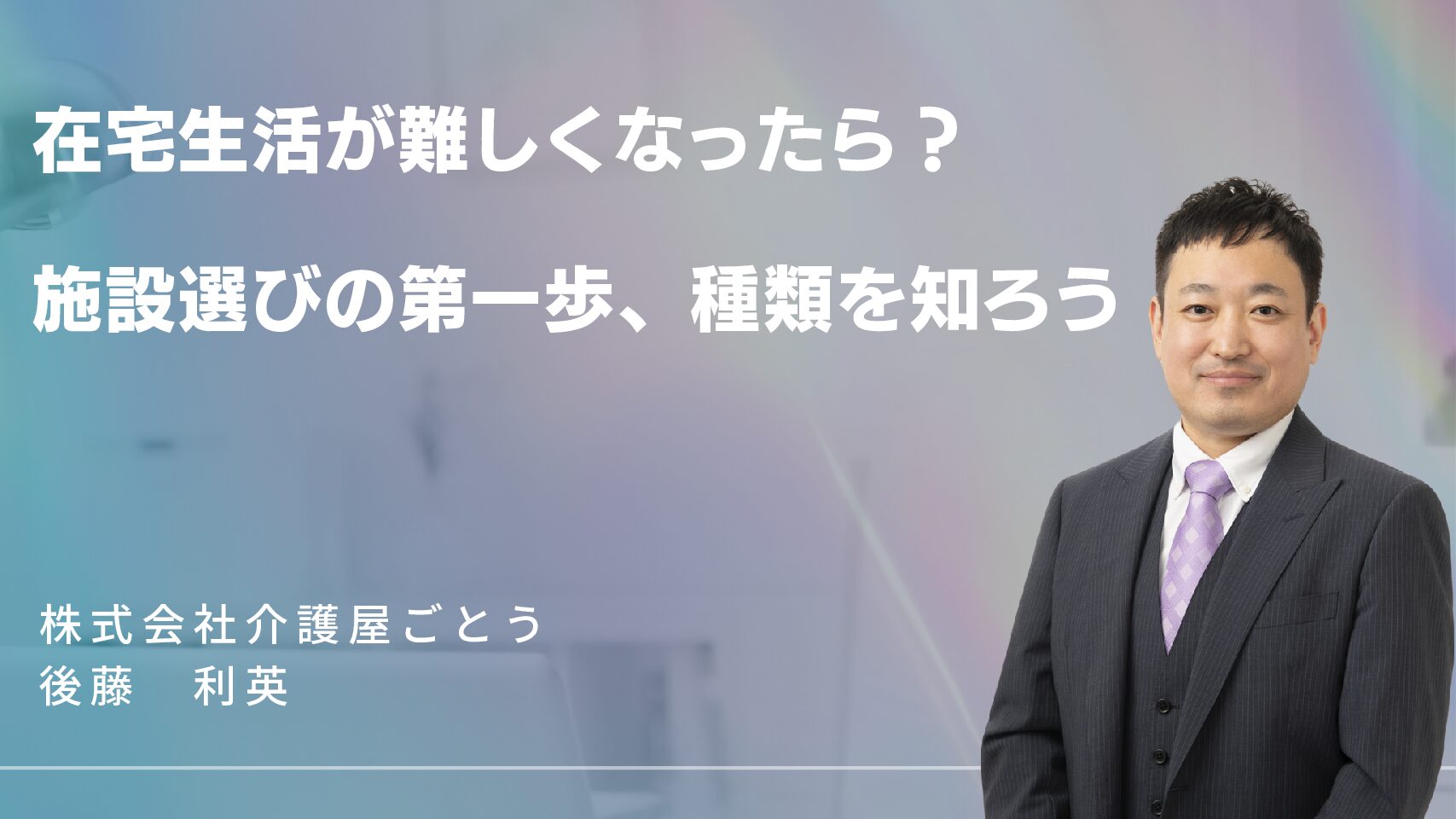在宅生活を続けられるか?――施設を検討する基準と備え方
食事が生活の質を左右する
食事は健康の基本であり、生活のリズムや楽しみにもつながります。
- 調理ができなくても工夫次第で在宅生活は可能
フードデリバリーを注文できる、毎日配達される宅配弁当を受け取れる、冷凍弁当を電子レンジで解凍できるなど、代替手段を使 えていれば問題ありません。 - 食べ物があるのに食べられないのは要注意
買い置きや宅配があるのに食事量が減っている場合は、体力や健康状態の低下のサインです。 - 食事や水分摂取でむせ込みが増えてきたら危険信号
誤嚥性肺炎のリスクが高まるため、専門的な対応や施設での生活を検討する必要があります。
👉 基準は「準備できるか」ではなく「安全に、十分に食べられているかどうか」で判断してください。
排泄は“清潔を保てるかどうか”
排泄の問題は、在宅生活の大きな分岐点です。
- 失禁後も自分で着替えや後始末ができれば大丈夫
オムツや尿取りパッドに抵抗がなく、清潔を保てていれば在宅継続は可能です。 - 後始末ができなくなると限界が近い
処理ができず不潔な状態が続けば、感染症や皮膚トラブルにつながります。 - 認知症による誤った行動が出始めたら要注意
使用済みオムツをトイレに流す、排泄場所を誤るなどの行動は、在宅対応が難しくなるサインです。
👉 排泄は「本人や家族で清潔を保てるか」が判断基準となります。
服薬管理は“生活の安全”に直結する
内服や注射は、在宅生活を続けるうえで非常に重要なポイントです。
- 薬を自分で管理できれば安心
決まった時間に薬を飲める、インスリン注射を忘れずに打てる状態なら在宅生活は可能です。 - 飲み忘れや管理のミスが増えたら要注意
血液サラサラや糖尿病など、薬を飲まないことで命に関わるリスクがある場合は危険信号です。 - 対応策を相談することもできる
医師に相談して「1日1回にまとめられる薬に変更できないか」「インスリンの回数を減らせないか」を検討することができます。
また、訪問介護やデイサービスを利用する際に「内服確認」をお願いすることも一つの方法です。
👉 服薬管理は「命に関わるミスが起きていないか」が判断基準となります。
火の始末と転倒リスクは命に直結
安全面で特に注意が必要なのが火の扱いと転倒です。
- 火を使わず生活できれば安心
IH調理器や電子レンジ中心に切り替えていれば在宅生活は可能です。 - 火の不始末は大きなサイン
ガスコンロをつけっぱなしにする、電子レンジに不適切なものを入れるといった行動は命に関わるため、施設検討が必要になります - 転倒は要介護度を一気に高めるリスク
立ち上がりでふらつく、外出中に転倒が増える、骨折歴がある場合は特に注意。
手すりやセンサーで補えるうちは在宅も可能ですが、夜間も目が離せない状況では施設の方が安全です。
👉 火と転倒は「命に関わる事故を防げるか」が判断基準となります。
施設は“諦め”ではなく“安心の選択”
在宅生活を続けられるかどうかは、
- 食事 → 安全に、十分に食べられているか
- 排泄 → 清潔を本人で保てるか
- 服薬管理 → 命に関わるミスが起きていないか
- 火の扱い・転倒 → 命に直結する事故を防げるか
これらを総合的に見て判断することが大切です。
施設に入ることは「在宅を諦める」ことではなく、「本人が安全に、家族が安心して暮らしていける選択」です。
早めに話し合いと準備を進めることで、後悔の少ない選択ができるはずです。
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう