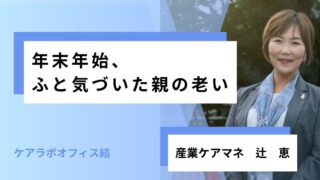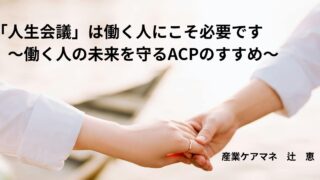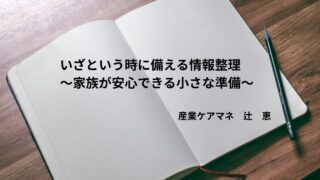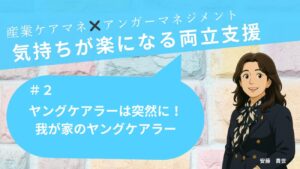介護休業は介護するための休みではない
こんにちは産業ケアマネの辻です。
私は、家族を介護した経験と、ケアマネジャーとしての経験と知識をもとに「親の介護」について発信しています。
今期も産業ケアマネを紡ぐ会のブログ担当させて頂きます、どうぞよろしくお願い致します。
今回は「介護休業」についてお伝えしたいと思います。
親の介護が始まる世代
超高齢社会となった今日、5人に1人が75歳以上の後期高齢者となります。
そしてその子ども世代が、働き盛りの40代、50代です。
40代、50代と言えば、会社では管理職になっていたり、キャリアを重ねて指導的立場になっていたりと仕事をバリバリとこなしている世代かと思います。
ちょうどその時期に、元気だった親が突然倒れたり、徐々に弱ってきて手助けが必要になり、介護が始まることが多いです。
部下や同僚に迷惑をかけるくらいなら、いっそのこと仕事を辞めて介護に専念する。そのように考えて仕事を辞めてしまう人が多くおられます。
「介護離職」です。
これは、個人や家族の問題にとどまらず、企業にとっても大切な人材を失い、生産性が低下して経済的な損失も大きなものとなります。
介護離職は社会全体に大きく影響を及ぼす問題となっているのです
また、介護離職までいかなくとも、介護をしながら働くことで、仕事のパフォーマンスを低下させる原因となることがあります。
こうした問題を受け国も仕事と介護を両立させるための政策を打ち出しています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)です。
この法律の中では、できるだけ現在働いている職場で仕事を続けながら介護をできるように、いくつかの休業制度が設けられています。
その一つが「介護休業」です。
介護休業とは
厚生労働省では以下のうように定義されています。
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の
厚生労働省 介護休業制度特設サイトより
期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
要介護状態にある家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます。
パートさんやアルバイトの方、派遣社員の方も一定の要件を満たせば取得できます。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/
93日もお休みが取れる!
いやいや93日しかお休みが取れない、、、
皆さんどのように感じますか。
休業制度というと、育児休業と比較できるかもしれませんね。
育児休業と介護休業との違い
育児休業は、1歳未満(条件によって最長2歳まで)の子どもを育てるために、労働者が取得できる休業制度です。
育児休業の目的は、育児と仕事の両立を支援することで、男女ともに育児に関わることができるようにすることです。
休業している間に、親として育児に専念して子どもさんと関わる時間を確保する制度です。
保育園に預けられるようになるまで、家庭でずっと育児をするわけです。
これに対して介護休業は、家族が要介護状態になった際に、仕事を休んで家族の介護に向き合う制度です。
育児制度と違うのは、要介護の家族を介護をする時間を確保するということではありません。
93日間の休みの間に、従業員が介護に専念するということではないのです。
介護は育児と違って、だんだん手がかからなくなるものではありません。むしろ、どんどん大変になっていきます。93日間で終わることはまずないですよね。
介護休業は、介護に専念する時間ではなく、介護の体制を整える時間なのです。
介護休業の使い方
介護体制を整えるとは、今後の介護に向けた準備や手続きを進めること。
必要なサービスや制度を利用して介護を継続できるように調整することです。
在宅での介護を想定した場合、具体的には以下のようなことが挙げられます。
介護の専門職と連携
- 要介護認定の手続き(地域包括支援センターへ相談)
- ケアマネジャーとの話し合い(家族の介護のための適切なサービスや支援の組み合わせを考える)
- 通院に付き添うなどして、必要に応じて医療職(訪問看護師、かかりつけ医)との話し合い
自宅の環境を整える(介護の環境づくり)
- 自宅のバリアフリー化(手すり設置、段差解消など)を検討する
- 必要な介護用品を検討する
要介護認定が出ると、介護保険福祉用具をレンタルしたり、住宅改修ができます。ケアマネジャーに相談して手続きを進めましょう。
家族の役割・協力体制を決める
- だれが何を担当するか(通院の付き添い、金銭管理、話し相手など)
- 遠方の家族にも「情報共有」や「できる範囲の支援」を要請する。
一人に負担が集中しないようにすることが大切です
仕事と介護の両立させるためにライフプランの見直し
- 今後の介護の見通しと、自分の働き方のバランスを考える
- 介護が長期化する場合に備えて、自分の働き方やキャリアの再設設計
介護をを抱え込まないために
介護休業の間、自分自身が率先して介護をするというのは私は間違いだと思っています。
間違いと言うと語弊があるかもしれませんが、会社を休んでいる間に一人で介護を抱え込んでしまうと、先が続きません。
たった93日しかない介護休業をいかに使うかによって、今後の介護の質が変わります。そして、介護する人の生活も左右されるのです。
頑張って全部やるではなく、いかに介護できる人(介護の専門職)・できる支援(介護に関する制度)に頼る体制づくりをするかだと思います。
介護休業の活かし方についてさらに知りたい方は、ぜひ私達産業ケアマネにご相談ください。
私は産業ケアマネとして、企業の経営者及び人事担当の方々、そして一般の方を対象に介護セミナーを行っています。
ご興味のある方は、下記までお知らせください!
↓ ↓ ↓ ↓
cm.megumi0925@gmail.com
プロフィールとポートフォリオ
↓ ↓ ↓ ↓
https://note.com/cm_kinako/n/n1809272508c7
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 1期卒業生
ケアマネージャー歴 10年
社会福祉士
介護福祉士
保育士
最新の投稿
 コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い
コラム2026年1月6日年末年始、ふと気づいた親の老い 産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜
産業ケアマネ向け2025年11月28日ケアマネジャーから産業ケアマネへ〜シフトチェンジに必要な視点と姿勢〜 コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜
コラム2025年11月17日「人生会議」は働く人にこそ必要です〜働く人の未来を守るACPのすすめ〜 コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜
コラム2025年11月6日いざという時に備える情報整理〜家族が安心できる小さな準備〜