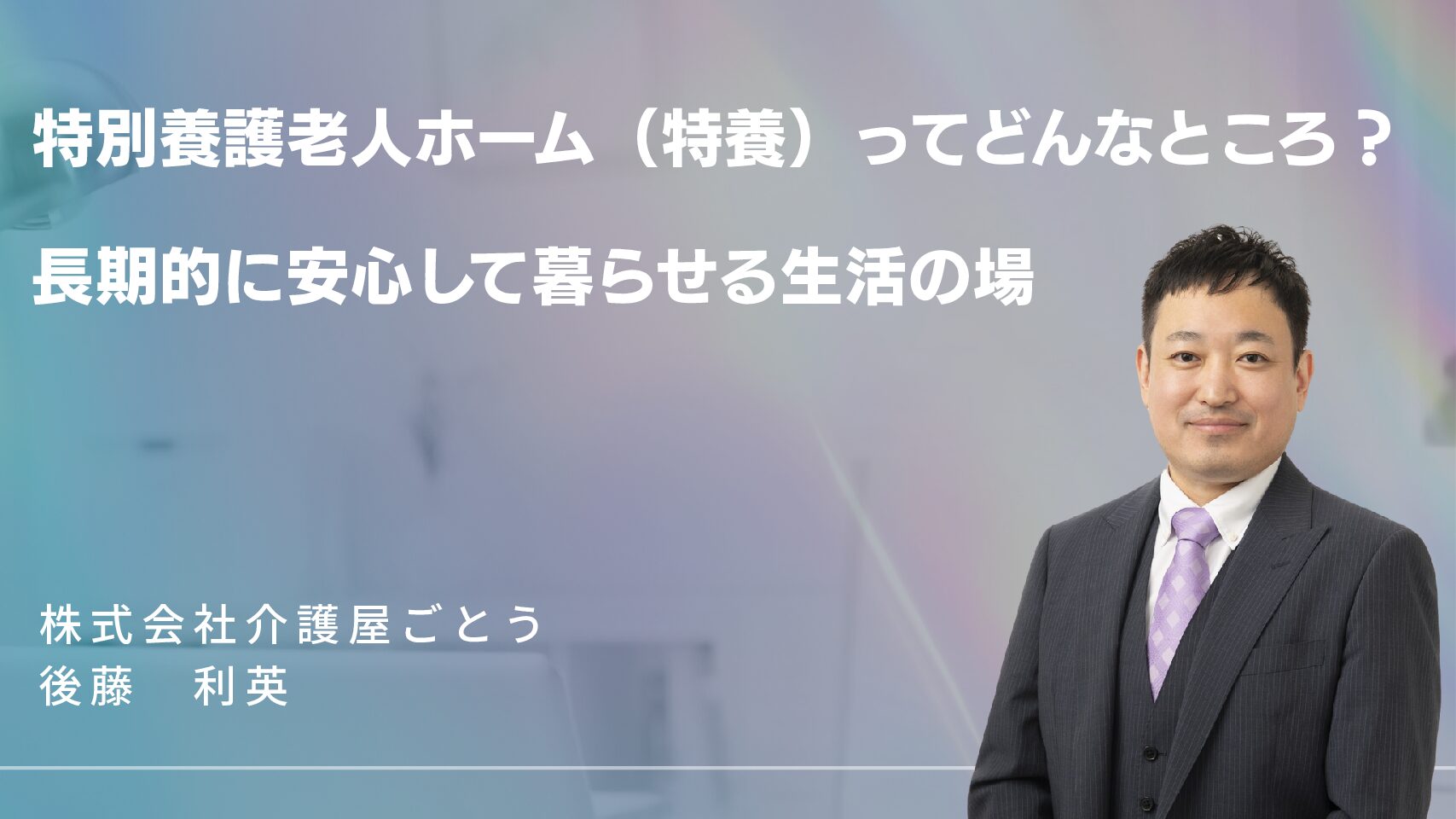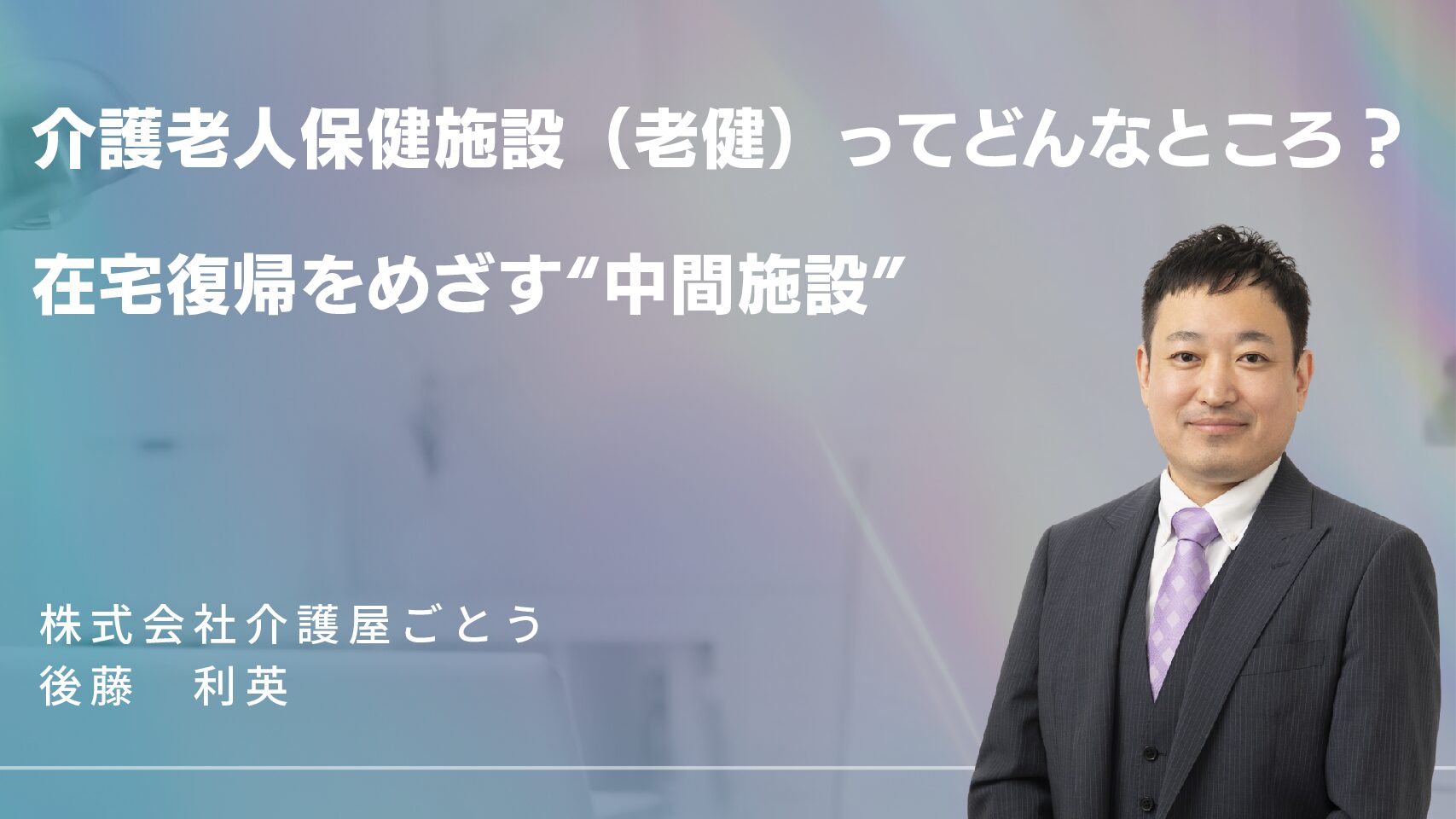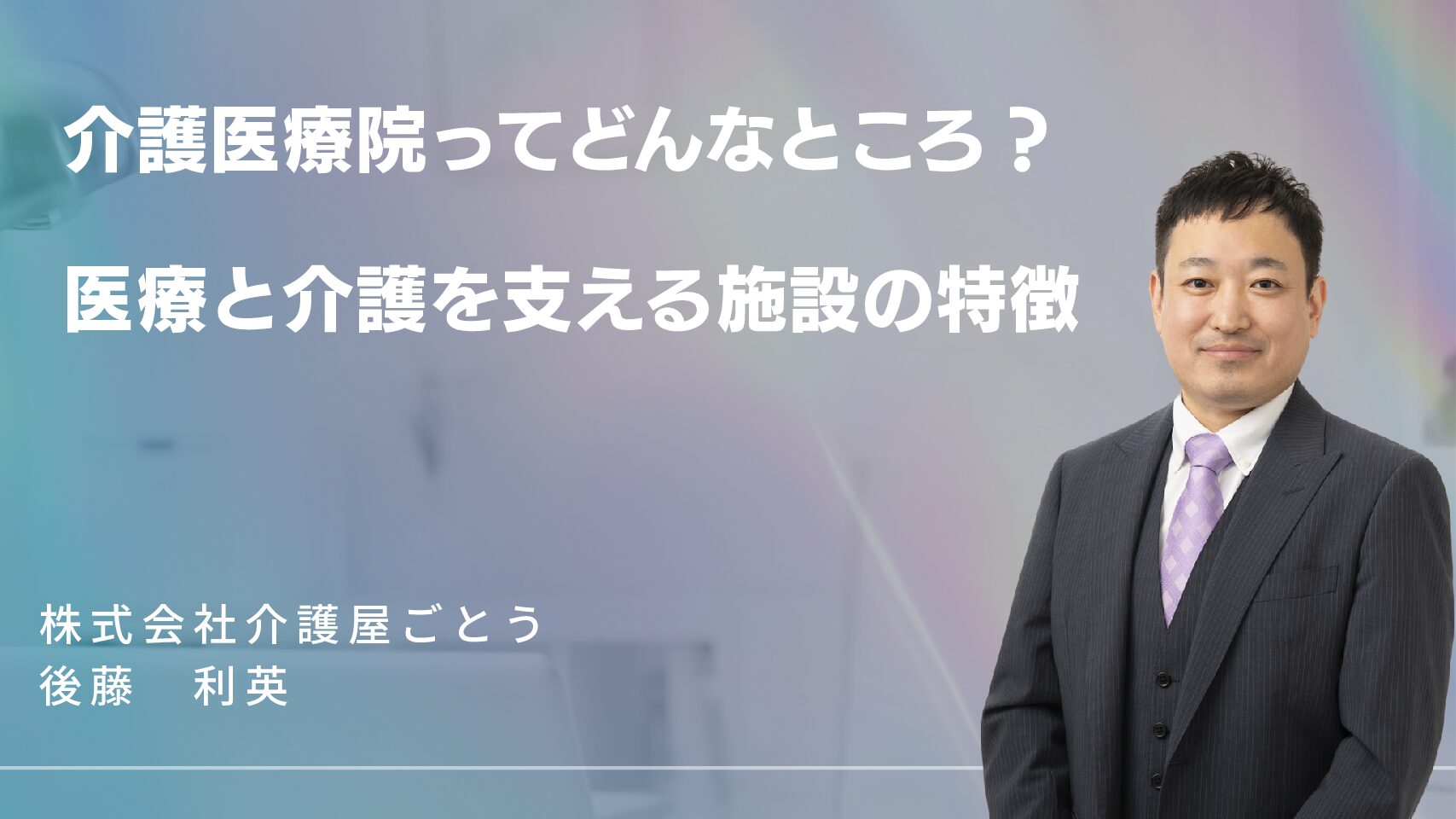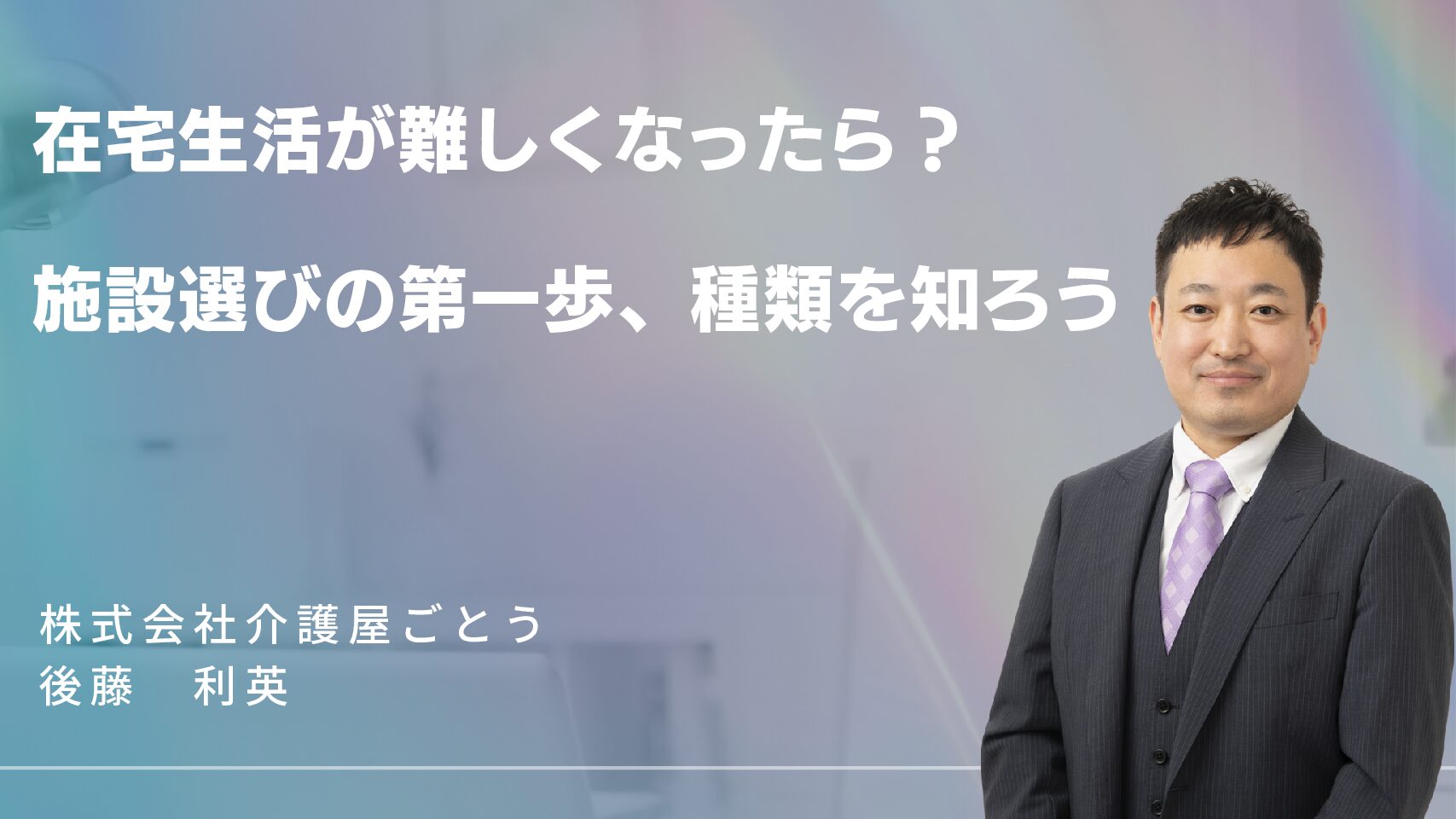介護は突然やってくる──“自分ごと”として向き合うためにできること
先日、【100年キャリア見える化ノート】を作成した渡邊先生主催のオンラインセミナーに登壇させていただきました。
参加者は社会保険労務士やキャリアコンサルタントなど、働く人のサポートをする専門職の方々。
その場で私が伝えたのは、「介護はすでに“労働の問題”でもある」という現実と、
産業ケアマネの役割、そして私たちが直面する“あるジレンマ”についてでした。
産業ケアマネの必要性が届かないジレンマ
私は産業ケアマネとして、仕事と介護の両立支援を行っています。
介護離職を防ぎ、働き続けられる環境を整えることが私の使命です。
しかし感じるのは、「産業ケアマネって必要なの?」「何をしてくれるの?」という反応がいまだに多いこと。
その背景には、「介護の問題はまだ自分には関係ない」「自分の親は元気だから大丈夫」といった意識があります。
「困った時に相談できる存在がいる」
そう知ってもらうには、困る前から伝えていかなければなりません。
だからこそ、私はこのセミナーで、“介護の現実”を少しでも身近に感じてもらえるようにしました。
100年キャリア見える化ノートは“自分ごと化”のツール
今回のセミナーでは、渡邊先生が開発した「100年キャリア見える化ノート」を活用しました。
私はこのノートを、キャリアの中にライフイベントや介護の可能性を“見える化”するためのツールとして利用しています。
私は介護が始まるきっかけや進行の過程を具体的な事例で説明しました。
たとえば、「遠方の親が転倒をきっかけに急に要介護状態になったケース」や
「介護とフルタイム勤務を両立しようとして心身ともに疲弊した会社員の話」など。
すると、すでに介護経験がある参加者からは、
「当時、こういう存在(産業ケアマネ)がいてくれたら、もっと楽だった」
という声があがりました。
また、まだ介護を経験していない方も、
「事例がリアルで、急に他人事じゃない気がした」
「ノートを使えば、準備の第一歩になる」
と感想を寄せてくれました。
介護を“自分の問題”として考えることが最初の一歩
今、社会全体が「介護があたりまえの時代」に向かっています。
厚労省のデータでも、50代〜60代の介護離職は年々増加しています。
それでも、働く人の多くが「自分はまだ大丈夫」と考えてしまうのは自然なことかもしれません。
だからこそ、「100年キャリア見える化ノート」のようなツールを使い、
未来の“介護と仕事”を今のうちから見つめておくことが必要です。
介護は、ある日突然始まります。
でも、備えることは今日からでもできる。
産業ケアマネは、その“備える力”を引き出すためのパートナーでもあります。
セミナーを通じて、「この存在をもっと早く知ってほしい」と改めて感じました。
まとめ
✅ 介護の問題が「自分ごと化」されない限り、支援の必要性は伝わりづらい
✅ 「100年キャリア見える化ノート」は介護を自分ごととして考えるきっかけになる
✅ 産業ケアマネは、働く人の未来を守るパートナー
これからも、こうした学びの場を通じて、
介護を“今から考えること”の大切さを広めていきたいと思います。
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう