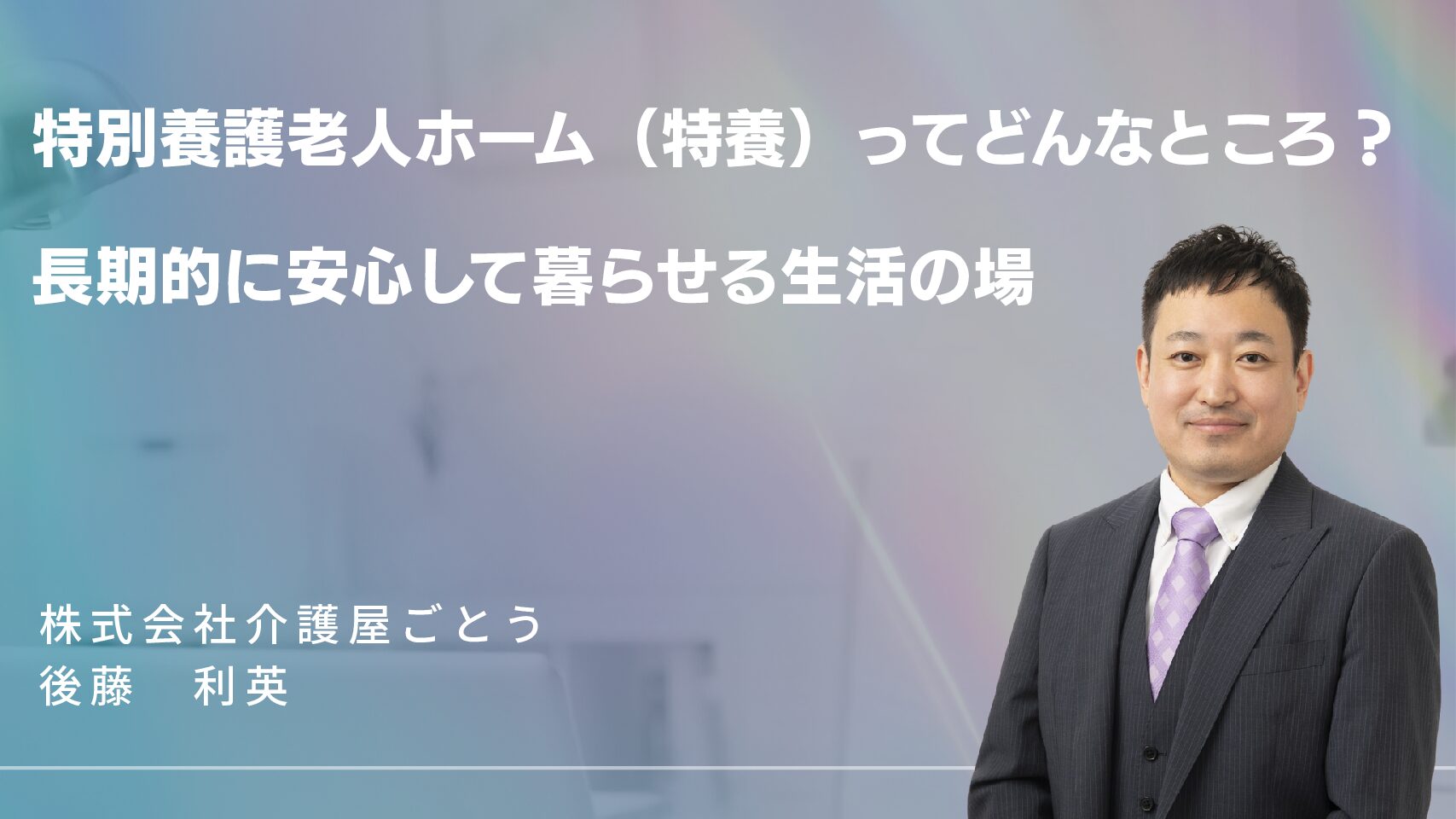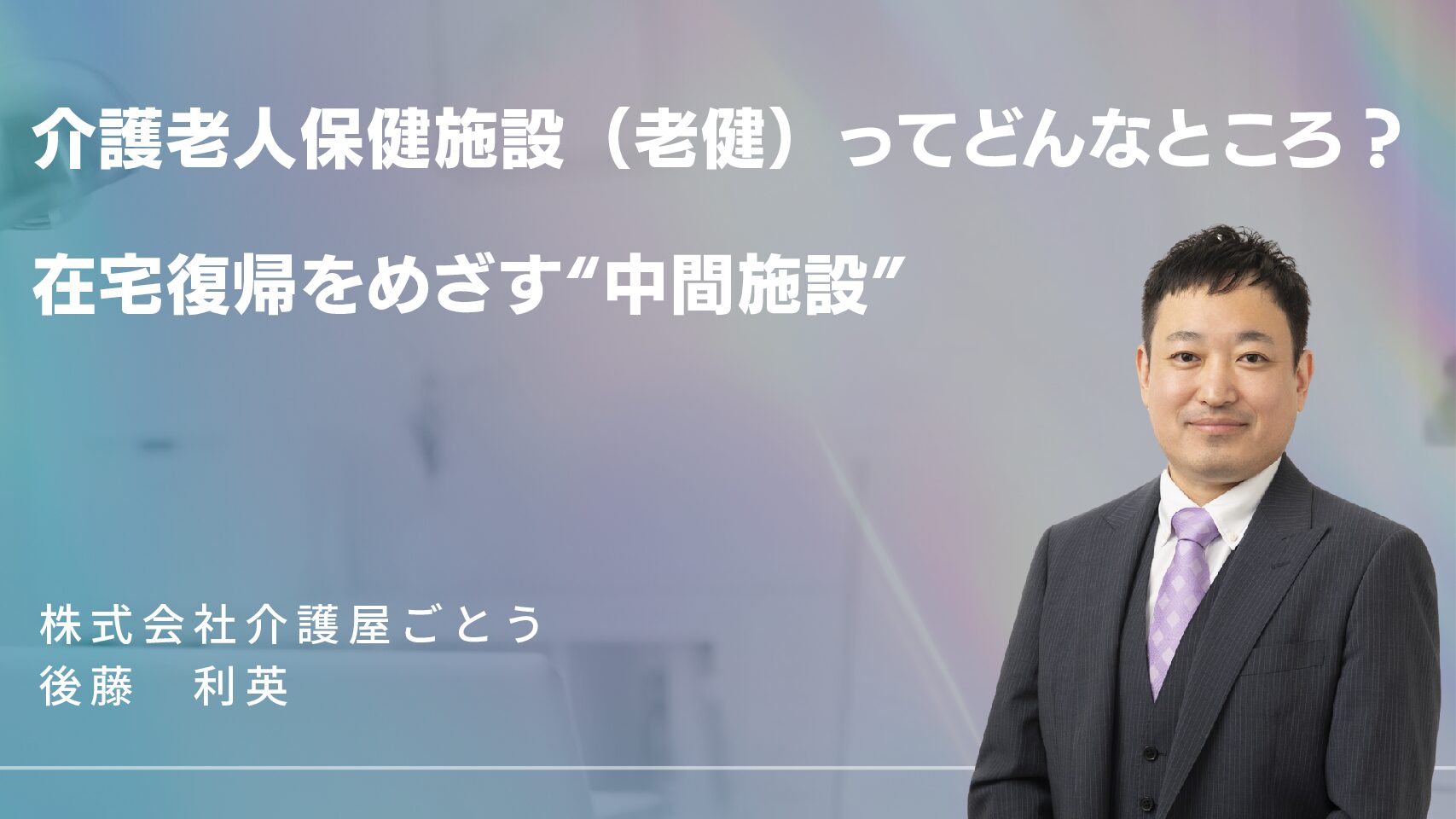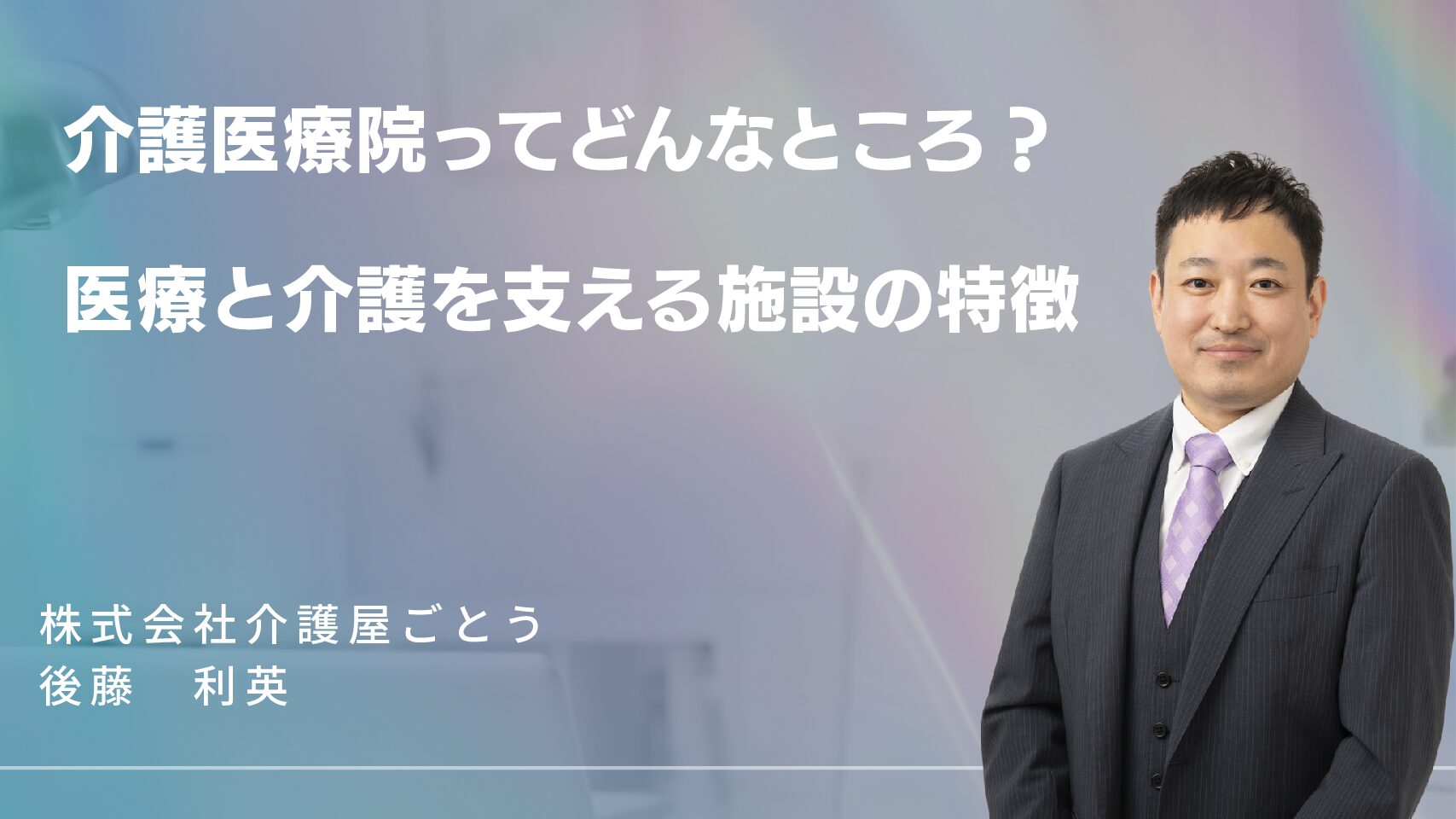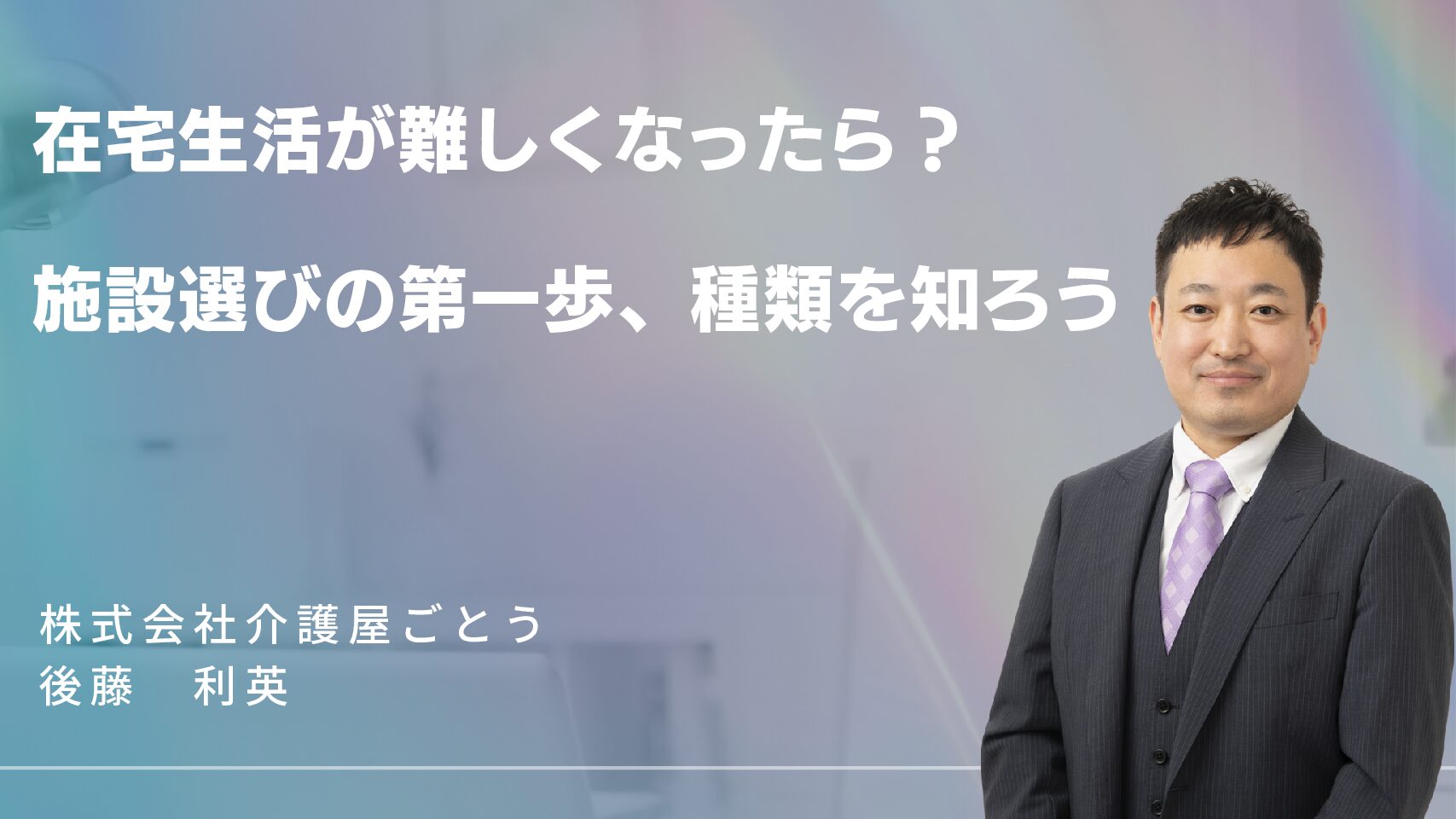介護はチーム戦!家族の役割分担で共倒れを防ぐ方法
介護の現場でよくある“温度差”問題
介護は「家族の誰かひとりが頑張ればいい」というものではありません。
しかし実際には、同居している人に負担が集中したり、遠方に住むきょうだいが「任せっぱなし」になったりと、家族間で大きな温度差が生まれがちです。
例えば、同居の長女がフルタイムで働きながら介護を担い、遠方に住む長男は「たまに電話で様子を聞くだけ」という状況。本人は悪気がなくても、同居家族は「私ばかりが犠牲になっている」と感じてしまい、ストレスがたまります。
この温度差を放置すると、家族関係の悪化や介護離職、共倒れにつながるのです。
役割分担は“できることをできる人が”
大切なのは「誰が一番頑張るか」ではなく、「誰が何を担えるか」です。
介護には身体介護だけでなく、通院付き添い、買い物、金銭管理、書類手続きなど多様なタスクがあります。
- 同居している人は食事や日常の声かけを中心に
- 遠方の家族は金銭面の支援や書類手続き、定期的な訪問を担当
- 仕事の都合で頻繁に動けない人は、見守りカメラやオンライン診療などの導入を担当
このように「できることをできる人がやる」という形で役割を明確にすると、不公平感が減り、家族みんなで支え合う実感を持てます。
産業ケアマネが家族会議をサポートします
とはいえ、家族だけで冷静に役割分担を話し合うのは難しいこともあります。
「私ばっかり負担している!」
「遠くに住んでるから無理だ!」
そんな感情のぶつかり合いが起こりやすいからです。
そこで活用していただきたいのが、産業ケアマネや地域のケアマネの存在です。
第三者として冷静に介護の現状を整理し、役割分担のバランスを一緒に考えることで、家族が前向きに協力できる場をつくれます。
介護は“チーム戦”。ひとりで背負う必要はありません。
家族で支える形を見つけよう
介護が始まると、「誰がどれだけやるか」で家族がギクシャクしてしまうことは珍しくありません。
でも本来、介護は「できることをできる人が」協力していくものです。
役割を分け合い、制度やテクノロジーも取り入れることで、介護はぐっと軽くなります。
そして、家族だけで抱え込まず、産業ケアマネのような専門家の力を借りることが、共倒れを防ぐ大切な一歩です。
介護は“チーム戦”。一人の犠牲ではなく、みんなで支える仕組みをつくっていきましょう。
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう