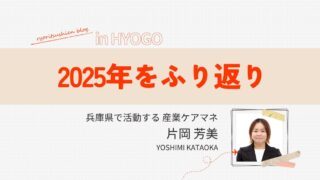介護の備えシリーズ② 気持ちの備え 〜自分の“軸”をもっておく〜
兵庫県で活動している 産業ケアマネの 片岡です。
介護に関する備えと聞くと、「制度」や「お金」など“目に見える準備”をイメージしがちです。
でも実は、介護の入り口で多くの人がつまずくのは「心の準備ができていなかった」こと。
親が老いるという現実を前に、戸惑ったり、家族と意見が合わなかったり。
介護の悩みは、気持ちの面から始まることも多いです。
今回は、「気持ちの備え」をテーマに、自分の軸を見失わないために大切にしたい視点を考えてみたいと思います。
気持ちの揺らぎ、いろいろあります
介護が始まると、多くの人がこんな気持ちに直面します。
- 「なんで自分ばっかり…」と感じる不公平感
- 「まだ大丈夫」と現実を直視できない戸惑い
- 「ちゃんとできてるのかな」という自信のなさ
- 「あのとき、もっと○○しておけば…」という後悔
- きょうだいや親との価値観のズレによるモヤモヤ
こうした気持ちは、決して特別なものではありません。
介護は、自分の暮らしと家族の関係性の“深いところ”が揺さぶられる体験だからです。
介護は、精神的にしんどい
制度やサービスの話よりも先に、気持ちの揺れに押しつぶされそうになる——
そんな人を、現場でたくさん見てきました。
「何が正解かわからない」
「自分の判断が、親を苦しめてないか不安」
「家族なのに、うまくいかない」
これは、介護の“あるある”です。
だからこそ、自分が何を大切にしたいのか。
周りと違っても「ここは譲れない」と思えることは何か。
——そんな“自分の軸”があると、心の揺れにも飲み込まれにくくなります。
「自分を大切にできる時間」を持っておく
介護の渦中にいると、「自分のことは後回しにしなきゃ」と思いがちです。
でも、自分をすり減らしてしまうと、介護も続かないのが現実。
だからこそ、今のうちに「自分にとって心地いいこと」を知って、それを大切にできる時間を持っておくのも、ひとつの備えです。
たとえば、
・趣味を大切にする時間をもつ
・一人で行くお気に入りの場所をつくる
介護が始まると、どうしても「やるべきこと」に追われがち。
でも、それだけに振り回されていると、いつしか心がすり減ってしまいます。
私が以前、ケアマネジャーとして関わらせていただいた介護者である家族様は、ずっと続けていたフラダンスを介護が始まっても続けておられました。
「介護は大変だけど、フラダンスや仲間との交流でリフレッシュできるしがんばれる。」
とイキイキと語っておられた姿がとっても印象的でした。
小さなことでも、自分が“自分らしくいられる時間”を手放さないこと。
それが、介護を続けていくための大きな力になります。
気持ちの備えは、“自分を大切にする”ことから
誰かを支えるって、とても体力も気力もいること。
だからこそ、「自分にとって大切なもの」を、少しずつ見つけておく。
気持ちの備えとは、決して特別な準備ではなく、「自分を大切にする力を養っておくこと」なのかもしれません。
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 講座2026年1月14日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る①「社会の仕組みを使う」とは?
講座2026年1月14日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る①「社会の仕組みを使う」とは? 講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは
講座2026年1月7日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜はじめに〜『家族だけで抱えない仕組みを、最初からつくる』とは コラム2025年12月30日2025年をふり返り
コラム2025年12月30日2025年をふり返り コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン
コラム2025年12月27日2026年の両立計画③「無理なく続ける」を目指す1年プラン