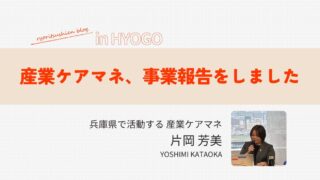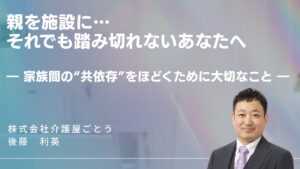両立支援の理解促進について考える。〜経営層編〜
兵庫県で活動している 産業ケアマネ 片岡です。
仕事と介護の両立というテーマは、これまで“個人の努力”に委ねられてきました。
しかし今、国の政策や企業実態はそのステージを超え、「組織として対応すべき重要課題」と位置づけられ始めています。
その象徴の一つが、経済産業省が発表している「仕事と介護の両立支援に関するガイドライン」です。
このガイドラインでは、企業が段階的に両立支援を進めるためのステップが明示されていますが、その第1ステップが『経営層のコミットメント』です。
「仕事と介護の両立」は、今や経営戦略の一部
経産省のガイドラインでは、まず経営層が「両立支援の必要性」を理解し、自ら発信していくことが重要であると述べられています。
- 経営トップ自らが、仕事と介護の両立の重要性を理解する
- 社内に向けて「企業として支援する姿勢」を表明する
- 推進のための体制を整える(専任担当、制度整備、外部連携など)
つまり、企業が両立支援に本気で取り組むかどうかは、経営者の“意思”にかかっているのです。
両立支援は「経営リスクの最小化」であり、「成長戦略」である
仕事と介護の両立支援を企業が怠ると、どんなリスクがあるのか。
経産省の資料では、以下のような「企業が直面する経営リスク」が挙げられています。
- キーパーソンの突然の離職・長期休職による人材損失
- 介護によるパフォーマンス低下による生産性の損失
- 組織の混乱、職場への悪影響(業務の属人化、疲弊)
一方で、支援をしっかりと行うことができれば、こんなポジティブなリターンが得られます。
- 有能な人材の離職防止・戦力維持
- 多様な働き方への対応力アップ(ダイバーシティの促進)
- 社外への企業価値の向上(「人を大切にする企業」としての信頼獲得)
- 顧客対応やサービスの安定供給
つまり、両立支援は“コスト”ではなく“投資”でもあるということです。
産業ケアマネという外部人材を、戦略的に活用する
しかし実際には「社内に専門的知見がない」「どこから着手すればいいかわからない」という声も多く聞かれます。
そのようなときに有効なのが、外部の専門人材と連携する選択肢。
たとえば、介護保険制度と両立支援の両面に精通した「産業ケアマネ」は、企業の両立支援体制づくりをお手伝いしています。
具体的には、
- 社内の実態調査(どれだけの従業員が支援を必要としているかを数値で把握)
- 社内外の資源の洗い出しと制度設計
- 両立に関する情報提供や研修
- 実際の従業員との個別支援対応(外部相談窓口)
などを通じて、両立支援における「人事・現場と経営層をつなぐ橋渡し役」を担います。
両立支援は、“福祉”ではなく“経営”の一部である
介護支援というと、「困っている人への福祉的配慮」として捉えられがちです。
しかし実際には、戦力を維持し、組織全体の持続可能性を高めるための“経営戦略”そのもの。
かつてない高齢社会の到来、大介護時代を迎え、今後ますます加速する「仕事と介護の両立時代」において、その成否は経営者のコミットメントにかかっています。
両立支援の旗を、社長・経営層が掲げるその一歩一歩が、職場に安心を生み、人と業績を支える力になっていく。
産業ケアマネは、そんな経営層のみなさんと力を合わせ、これからの時代に選ばれる企業づくりをお手伝いしていきたいと考えています。
お問い合わせはコチラ
私、産業ケアマネ 片岡 は
主に兵庫県の企業様を対象に「仕事と介護の両立支援明石事務所」を運営しています。
社内セミナーや社内実態調査、介護に直面する従業員への個別面談などを通じて仕事と介護の両立を支援。
社会問題「介護離職」の防止につなげます。
企業代表者様、人事担当者様、お気軽にお問い合わせください!
mail:ryoritsuakashi@gmail.com
お問い合わせフォーム(←クリック)
Instagram(←クリック):鋭意更新中!フォローしていただけたら嬉しいです♪
投稿者プロフィール

-
産業ケアマネ2級
仕事と介護の両立支援コンサルタント養成講座 2期卒業生
介護業界21年
社会福祉士/介護支援専門員
仕事と介護の両立支援明石事務所 2024年11月開設
最新の投稿
 コラム2026年2月25日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』②まじめな人ほど、仕事と介護の両立が苦しくなる理由
コラム2026年2月25日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』②まじめな人ほど、仕事と介護の両立が苦しくなる理由 産業ケアマネ向け2026年2月21日産業ケアマネ、事業報告をしました
産業ケアマネ向け2026年2月21日産業ケアマネ、事業報告をしました コラム2026年2月18日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』①介護が始まった瞬間、キャリアの分かれ道はもう始まっている
コラム2026年2月18日介護が始まった瞬間『キャリアの分かれ道』①介護が始まった瞬間、キャリアの分かれ道はもう始まっている 講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像
講座2026年2月11日少子高齢社会の在宅介護を乗り切る〜まとめ〜家族だけで抱えない介護を実現するための全体像