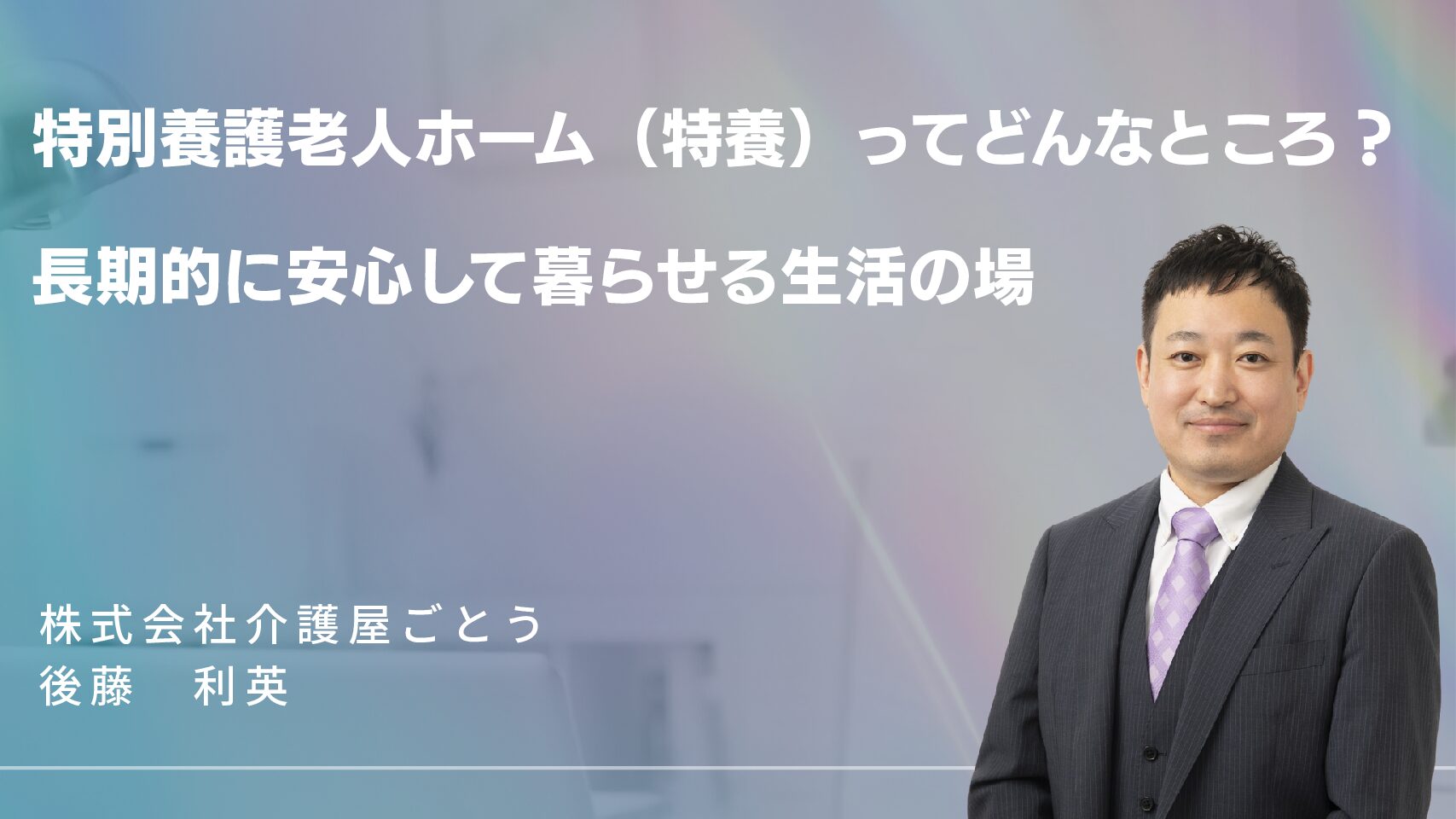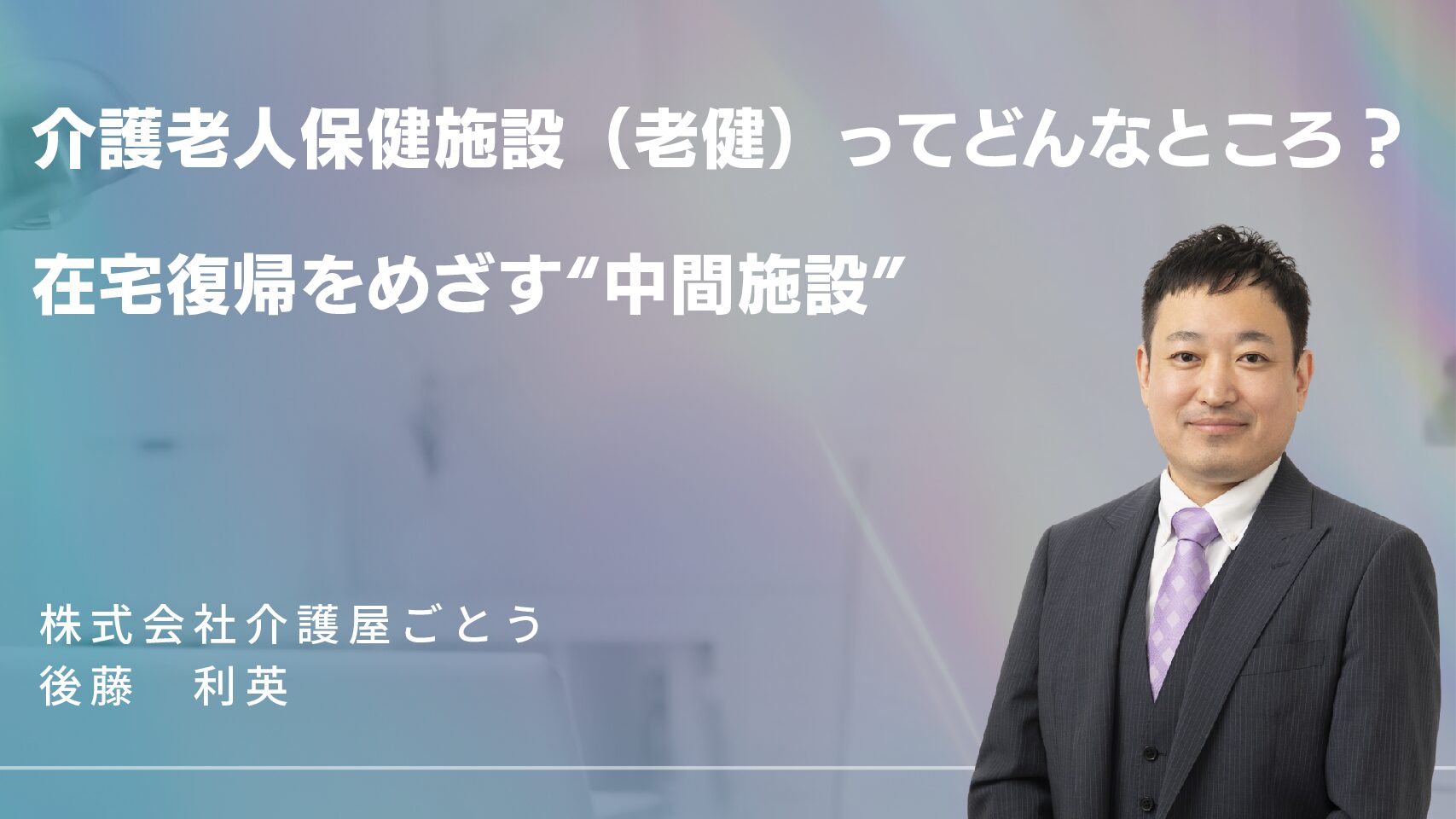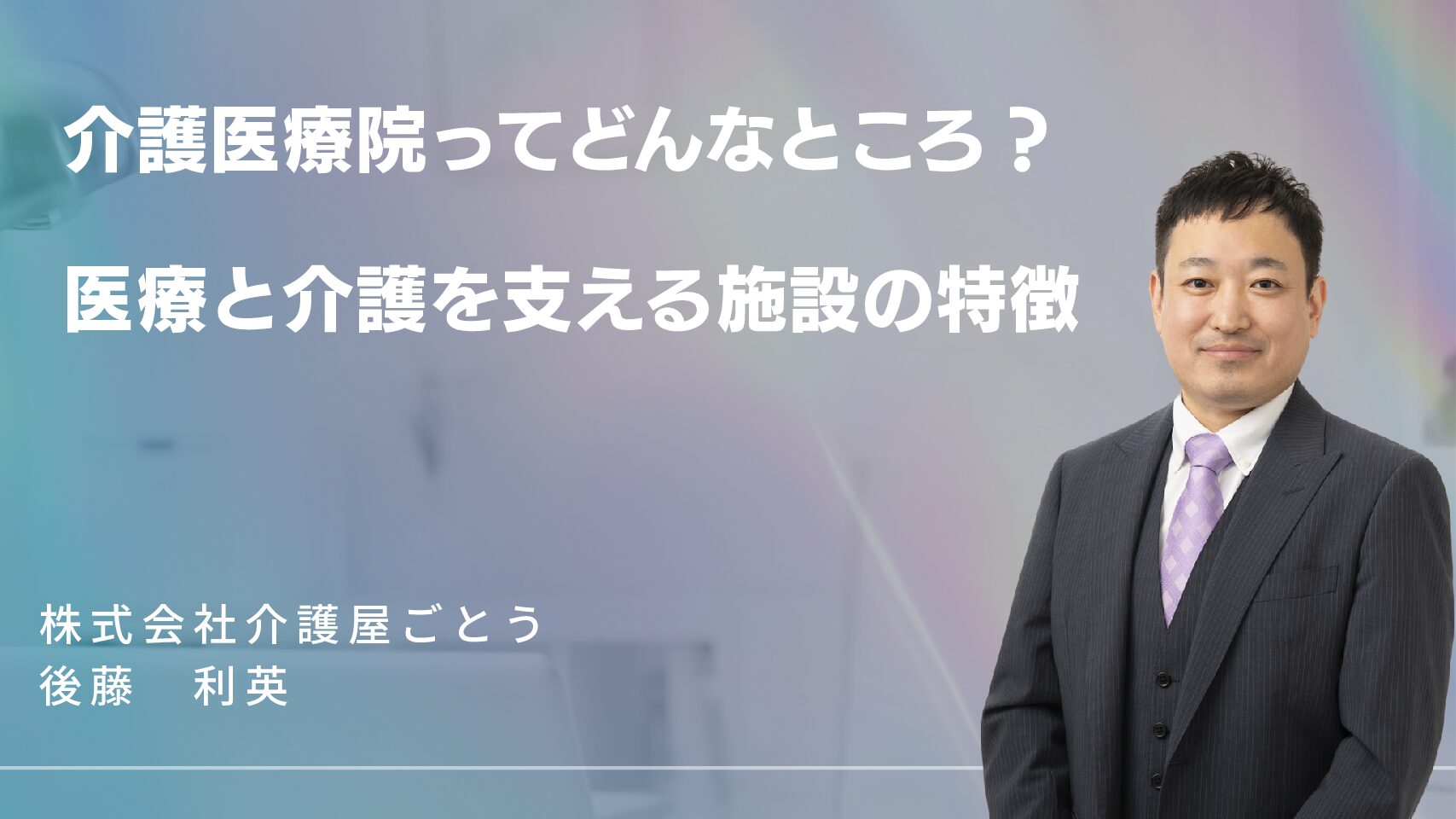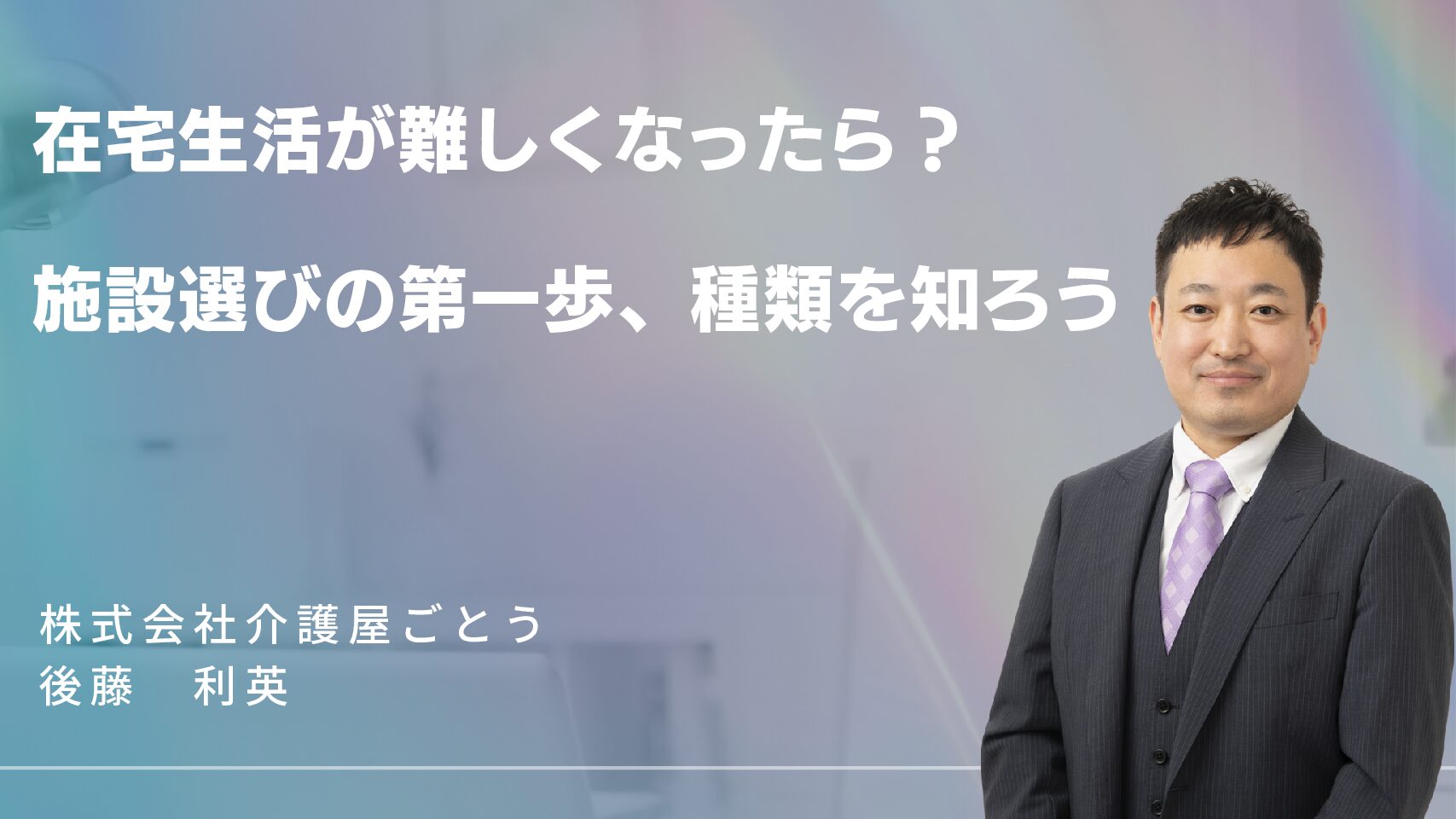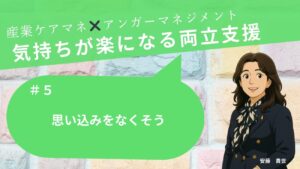「認知症になっても、すべてを失うわけじゃない」
認知症の本当の姿を知るために
「認知症」と聞くと、どんなイメージを持つでしょうか?
もしかすると、「何もわからなくなる」「家族が誰かわからなくなる」といったネガティブな印象が浮かぶかもしれません。
でも、実際の認知症は、そんな単純なものではありません。
認知症になっても、人は人のまま。
想いも、願いも、確かにそこにあります。
今回は、認知症の基本的な知識とあわせて、長谷川和夫先生や丹野智文さんの言葉を通して、
「認知症を正しく知り、受けとめる」ためのヒントをお伝えします。
「認知症にもいろんな顔がある」
認知症とは?まずは種類と特徴を知ろう
認知症とは、いろいろな病気や原因によって「記憶・判断力・認識」などに障害が生じ、日常生活に支障が出る状態をいいます。
代表的な種類と特徴を簡単にまとめると、次の通りです。
- アルツハイマー型認知症:記憶障害が中心。新しいことを覚えづらくなります。
- 脳血管性認知症:脳卒中などが原因。できることとできないことにムラが見られます。
- レビー小体型認知症:幻視や体の動きに特徴。初期は記憶が比較的保たれます。
- 前頭側頭型認知症:行動や感情コントロールに変化が出やすいタイプ。
「認知症=全部忘れる」というイメージは誤解です。
それぞれの認知症に特徴があり、残る力もたくさんあることを知っておきましょう。
「当事者が語る“認知症のリアル”」
「ボクはやっと認知症のことがわかった」から学ぶ、認知症の内側
認知症研究の第一人者であり、認知症の早期発見を目的とした「長谷川式簡易知能評価スケール」の開発者でもある長谷川和夫先生。
晩年、自ら認知症と診断され、体験者としての著書『ボクはやっと認知症のことがわかった』を世に送り出しました。
この本の中で、長谷川先生はこう語っています。
「今の私は、昔のように考えられないけれど、感じる心はちゃんと残っている」
「自分が何者かわからなくなる瞬間もある。でも、“人を大切に思う心”は、決して失われない」
認知症になると、できないことは確かに増えます。
けれど、「誰かとつながりたい」「愛したい」「愛されたい」という深い感情は、しっかりと生きています。
「認知症になっても、未来は続いている」
映画『オレンジ・ランプ』に見る、認知症の本当の姿
若年性認知症と診断された丹野智文さん。
彼の実体験をもとにした映画『オレンジ・ランプ』は、多くの人に勇気と希望を届けています。
診断当初、丹野さんは絶望しました。
「認知症になったら、何もできなくなる」という社会の偏見に押しつぶされそうになったのです。
けれど丹野さんは、ある日こう決意します。
「できないことに目を向けるのではなく、できることを数えよう」
そして現在、丹野さんは講演や執筆活動を通して、認知症の理解を広げるリーダーとなっています。
丹野さんの言葉はとても力強いです。
「認知症になっても、人生をあきらめる理由にはならない」
「わからないこともある。でも、笑ったり、感動したりする心はちゃんと残っている」
認知症になっても、人生は終わらない。
むしろ、「どう生きるか」を自ら選び直すことができる。
丹野さんの歩みは、認知症を「希望の物語」に変えていけることを教えてくれます。
「できないことではなく、“できること”に目を向けよう」
認知症になっても、人は生きている
認知症になっても、人は生きています。
- 家族を大切に思う心
- 仕事を続けたい気持ち
- 楽しい時間を過ごしたいという願い
これらは消えません。
できないことがあっても、できることを一緒に探していく。
それが認知症と向き合う本当の姿勢です。
産業ケアマネとして、働く人たちに伝えたい。
「認知症になったら終わり」ではないこと。
そして、親が認知症になっても、
私たちはまだ、たくさんの喜びやつながりを共に育むことができます。
認知症に対する正しい理解は、本人にも、家族にも、社会にも、大きな力になります。
今日から一緒に、学びを始めましょう!
投稿者プロフィール

-
大学卒業後、営業職・飲食業をへて介護業界へ。ホームヘルパー2級を取得後にグループホームでキャリアをスタート。
介護福祉士を取得し病院、ケアマネージャーを取得して老健・居宅支援事業所で働き、15年間の経験を元に、昨年7月株式会社介護屋ごとう、本年2月からはワントップパートナー札幌麻生店を設立。
最新の投稿
 コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場
コラム2025年10月3日特別養護老人ホーム(特養)ってどんなところ?――長期的に安心して暮らせる生活の場 コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設”
コラム2025年9月26日介護老人保健施設(老健)ってどんなところ?――在宅復帰をめざす“中間施設” コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴
コラム2025年9月19日介護医療院ってどんなところ?――医療と介護を支える施設の特徴 コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう
コラム2025年9月12日在宅生活が難しくなったら?――施設選びの第一歩、種類を知ろう